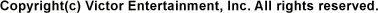|
 『素直に泣いたり笑ったりできる心地よさ』
『素直に泣いたり笑ったりできる心地よさ』アイルランド音楽は、ケルト民族の歴史が生み、育んできた。ケルト民族は古代ヨーロッパを一時支配していたが、その歴史は悲しみと苦しみの連続だった。人々は、そんな感情を音楽に託したのである。古代ケルト民族は文字を持っていなかったといわれ、音楽がケルト文化の大きな部分を占めるという結果にもつながったようだ。そこには、なにひとつ虚飾がない。ストレートな感情が、ダイレクトに聴く人の心に届く。音楽を聴いて、素直に泣いたり笑ったりできるというのは、とても心地よいことなんだと教えてくれる。いま、他にそんな音楽があるのだろうか。 『音楽は楽しむもの、という原点に帰るなら』 ケルト文化としての音楽は人から人へ伝わってきたものだが、一部の人たちのための「伝統」では決してなし。伝統が、あらゆる人々の間で生きている。街に出てみれば、それは一目瞭然。ごく普通の人々が、思い思いにストリート・パフォーマンスを繰り広げ、パブでは老若男女が一緒に歌ったり、踊っていたりする。「人に近い音楽」を象徴するシーンだ。それも、トラッドだけでなく、ポップスありジャズありで、実に楽しい。悲しみと苦しみの歴史を音楽に託したといっても暗いわけでなく、音楽は楽しむものだという気持ちに満ちていて、とても明るいのだ。  『あくまでも自然、人は皆そこに共感する』
『あくまでも自然、人は皆そこに共感する』アイルランドには、一種独特の自然が残っている。モイア・ブレナンは、そんな自然をみれば「地球に近い音楽」と表現した理由が実感できるだろうとも述べている。素朴なアイルランドの自然は、虚飾のないケルト・ミュージックと同じなのかもしれない。「飽和状態のファッション化」にさらされた現代人の心に、なんともいえない癒し感を与えてくれるのだ。ここでの自然とは、ムリがない、あるいは広いという意味をも含む。本音で歌う、伝統の音楽をこよなく愛しながら、ロックもポップスも受け入れる。世代も、まったく関係なしである。音楽がこれほど良質の潤滑剤になっている国は、おそらくアイルランドをおいて他にないだろう。世界のトップ・ミュージシャンたちに大きな影響を与えたケルト・ミュージックに、いま共感を持つ人々が確実に増えている。こうした現象に対して「?」マークをはさむ余地は、まったくといってよいほどないのだ。  ●アイルランドとケルト文化●
●アイルランドとケルト文化●[妖精と一緒に暮らすアイルランドの人たち] 古くから、ケルト人は神と妖精と英雄が関わりながら世界を作ると考えていた。現在でも、妖精は人々の生活に密接に結びついている。アイルランドは、妖精の国でもある。自然の中に身を置くと、確かにいまにも妖精が現れてきそうだ。日曜日には教会に行き、平日は妖精と過ごすとういう。この感覚は、いったい。 [ぜひ味わってみたいアイルランド料理とお酒] 隣国のイギリスとは異なり?アイルランドの食事は総じておいしい。ホテルやR&Bでは、ボリュームたっぷりのアイリッシュ・ブレックファースト。パブやレストランでは、さまざまなシーフードと野菜を素材にした料理が楽しみ。たとえばムール貝のクリーム煮などは、なかなかのもの。お酒では本場のギネスビールもいいが、世界一のシェアを持つリキュール「ベイリーズ」も試してみたい。さすがにアイルランドを代表するお酒という感じがして、なんともまろやか。そう、食事の料金がとにかく安く、日本とは大違いなのもうれしい。  [ちょっと意外なアイルランド]
[ちょっと意外なアイルランド]緯度は、日本の東北や北海道とほぼ同じ。といっても、冬に零下になることはほとんどない。暖流のおかげによるもので、そのためか人々はとてもおだやか。 [ちょっと身近なケルトの文化] ほとんどの日本人は、子供のころに実はケルト文化に触れている。それは、あの奇想天外な物語「ガリバー旅行記」である。ちなみに、250年前のアイルランドの人々にとって、日本は空想の世界と思われていた。 [ケルティック・アクセサリー] ケルトの装飾美術は、ケルト文化を代表するもの。そこに描かれた独特の文様は、宇宙や永遠を表現したものだという。世界で、日本で、ケルトの装飾美術を採り入れたグッズが人気を博し、海外のスーパーモデルや日本の人気アーティストも、リングやネックレスなどのアクセサリーを愛用している。 |