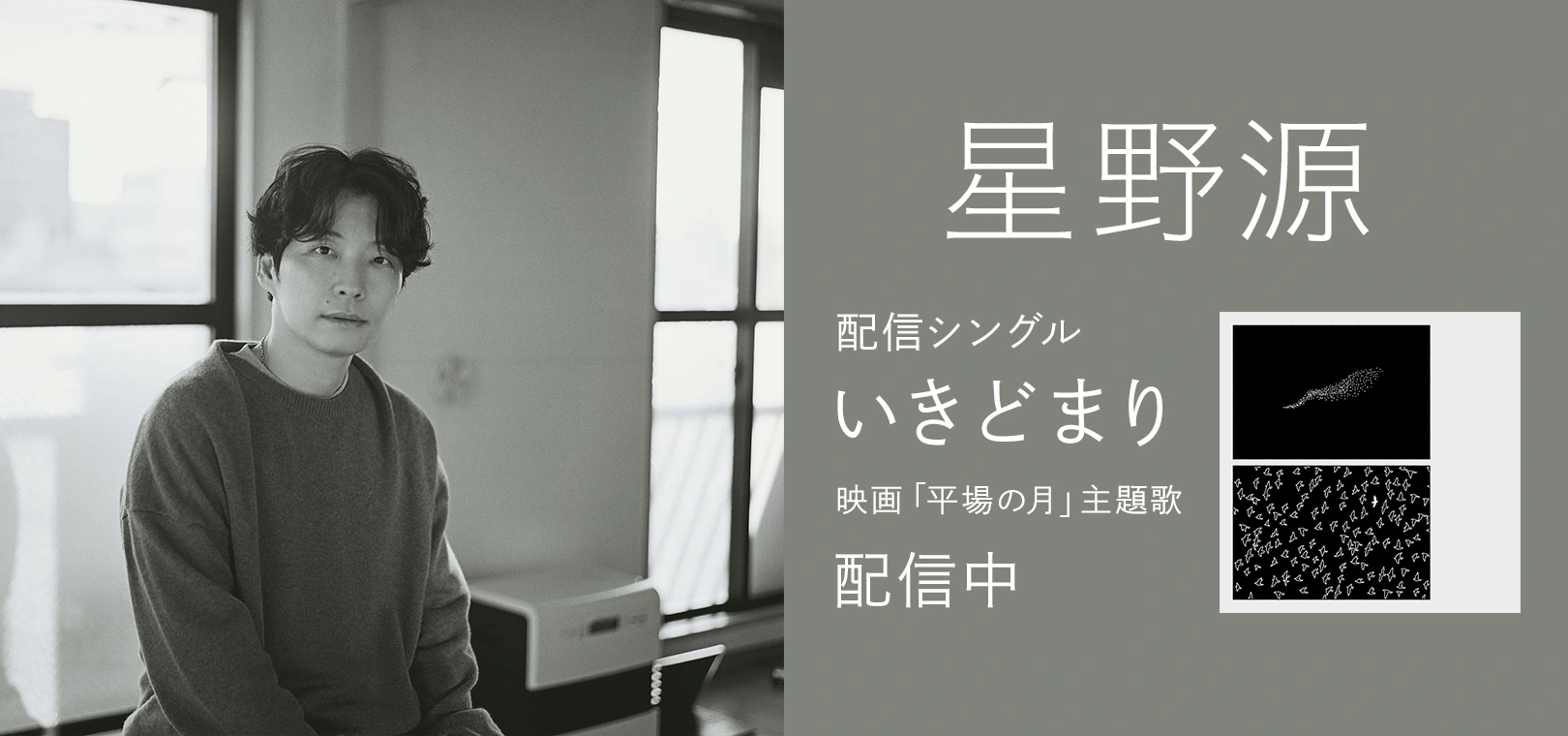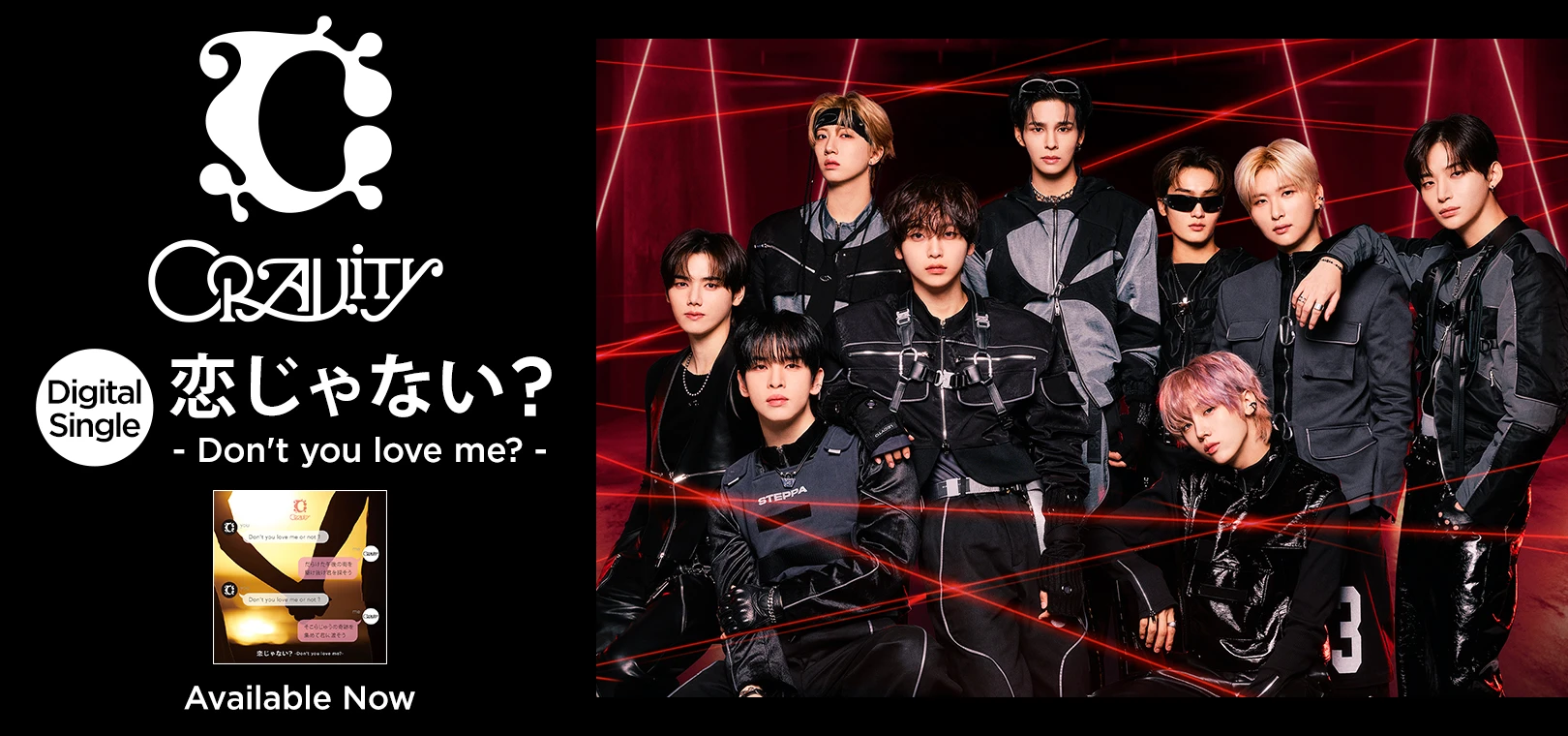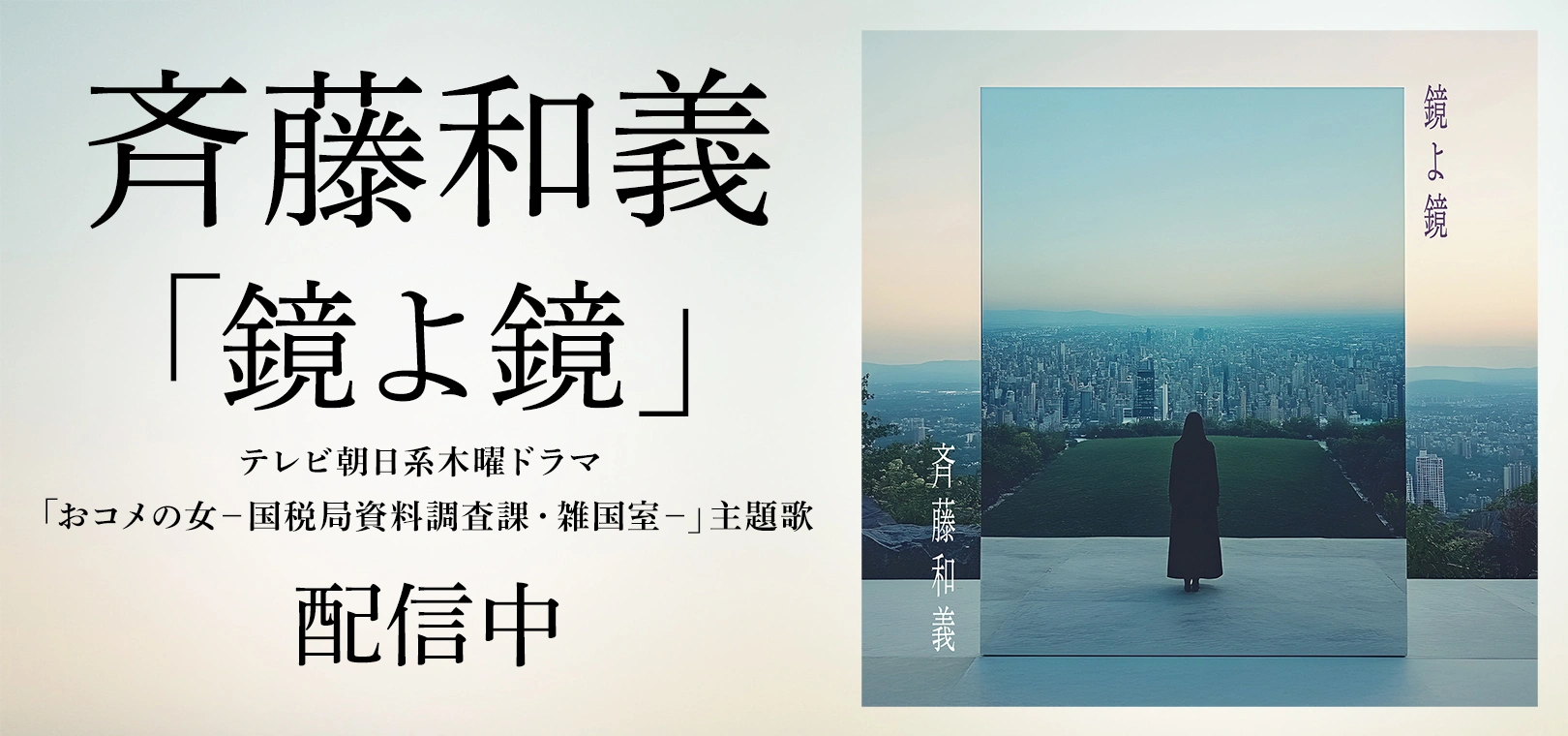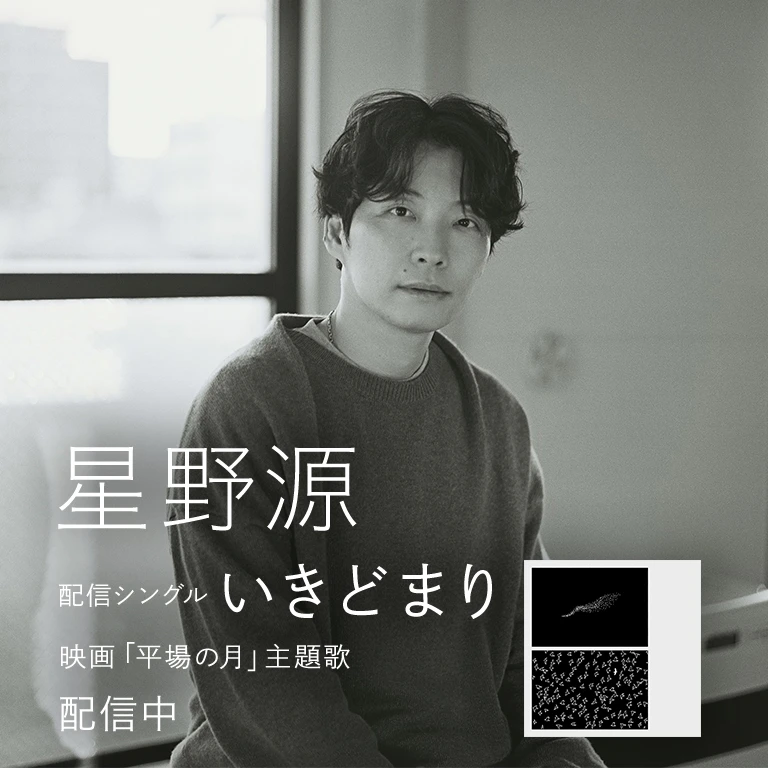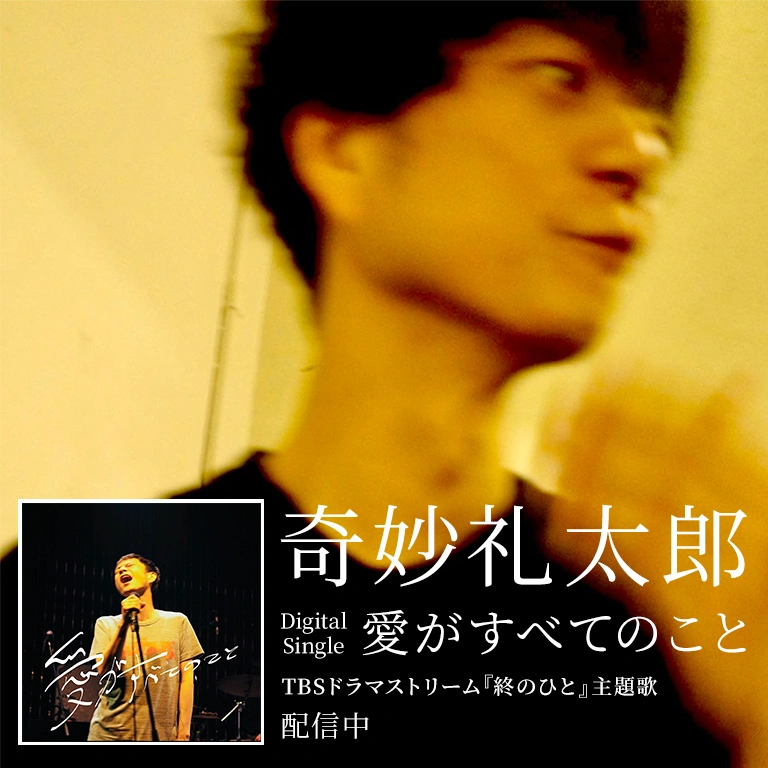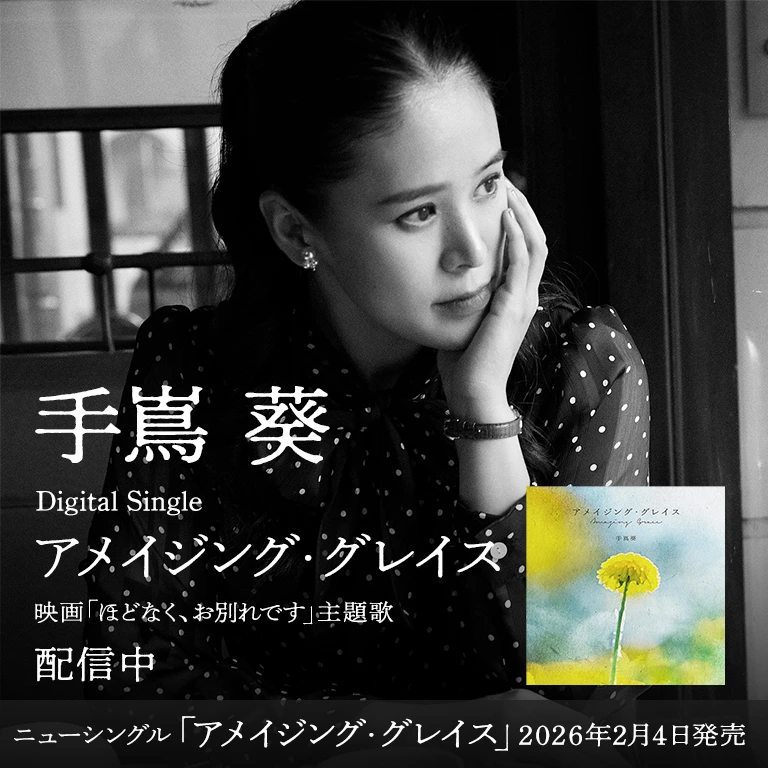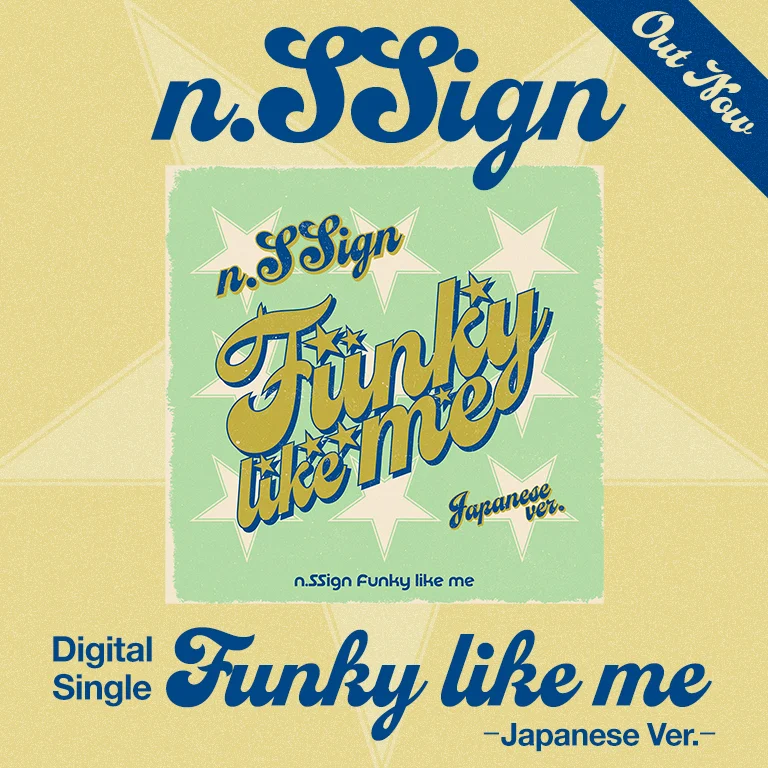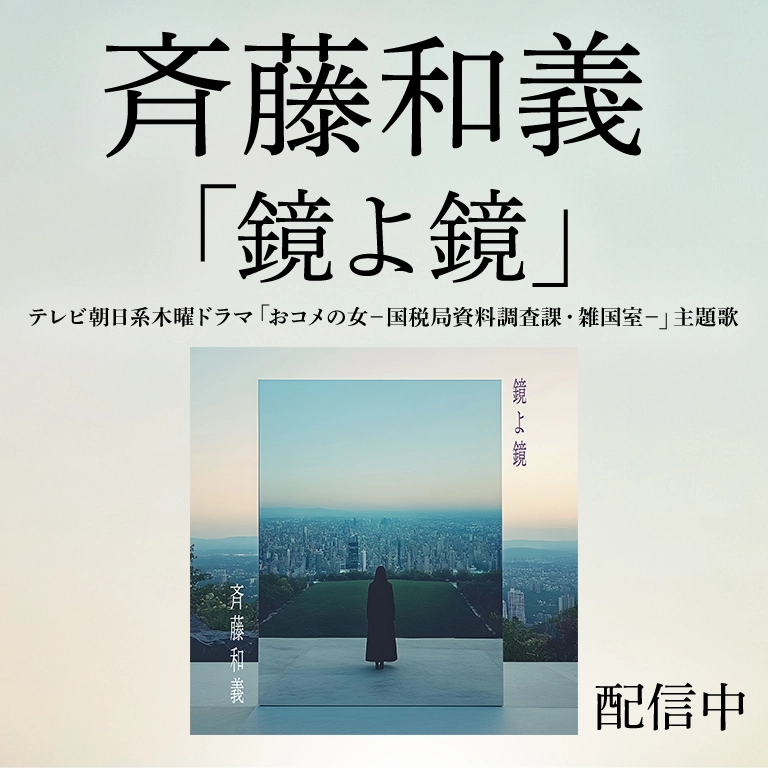伊良皆 高吉/岡山 稔/喜舎場 英勝
八重山謡

-
01
赤馬節 Akanma-bushi
-
02
鷲ぬ鳥節 Basuinutorui-bushi
-
03
鳩間節 Hatoma-bushi
-
04
月夜浜節~船越節 Tsukiyahama-bushi ~ Funakuya-bushi
-
05
大浦越地節 Ufarakuitui-bushi
-
06
小浜節 Kumoma-bushi
-
07
安里屋節 Asadoya-bushi
-
08
黒島節 Kurusuima-bushi
-
09
首里子節 Shuritsu-bushi
-
10
崎山節 Sakiyama-bushi
-
11
まるまぶんさん節 Marumabunsan-bushi
-
12
真南風乙節 Mafueratsu-bushi
-
13
千鳥節 Tsudorui-bushi
-
14
夜雨節 Yuruami-bushi
-
15
仲筋ぬぬべーま節 Nakasuzunu nubeema-bushi
-
16
みるく節 Miruku-bushi
【各曲解説】
01.赤馬節
*八重山を代表する格調高い祝宴歌。座開きの曲である。
02.鷲ぬ鳥節
*赤馬節と並ぶ、八重山を代表する祝儀歌である。若鷲の巣立ちを吉祥として雄大に歌い上げている。
03.鳩間節
*鳩間島の土地讃歌。鳩間島は土地が狭いため、西表島に舟で農作業に通ったという。
04.月夜浜節
*薩摩の人頭税時代、男は米粟、女は上布や木綿を納めなければならなかった。過酷な暮らしの中で、幻想的ともいえる美しい歌を生み出した八重山人の心が伝わってくる。手巾(ティサジ)とは、娘が愛情のしるしとして自ら織り、想う人にあげた布のこと。
05.船越節
*前曲の結びとしてうたわれる。
06.大浦越地節
*毎年、豊年祭などの祝いの場で歌われる。険しい山道を色々な配慮をして、役人を出迎えた様子を歌ったもの。
07.小浜節
*小浜島の土地讃歌。8・8・8・6の琉歌形である。
08.安里屋節
*赴任してきた役人の現地妻にまつわる話である。これをもとにして昭和9年、星克作詞、宮良長包編曲で「安里屋ユンタ」となり全国的にヒットした。
09.黒島節
*黒島の祝儀歌。沖縄本島に伝わり、舞踊『松竹梅』の「鶴亀踊り」に取り入れられている。
10.首里子節
*首里子とは、赴任してきた役人と現地妻との間に生まれた子のこと。男の浮気を弱い者の立場から綴った物語歌謡。八重山一円に伝承される首里子ユンタである。
11.崎山節
*1775年、波照間島から西表島の未開地に女100人、男80人が強制移住させられた。だが急傾斜の地とマラリヤのためついに廃村となる。ジャングル開拓の辛さと、望郷の思いを歌ったものである。
12.まるまぶんさん節
*丸島盆山とは西表島祖内湾の中にある小島のこと。丸い盆のような島と、辺りの美しい風景を歌っている。
13.真南風乙節
*幼くして親と死に分かれ苦労を重ねた娘の物語歌。最後には良い若者に出会い幸せな結末で終わる。
14.千鳥節
*鳩間島の十二ヶ所の浜に舞い飛ぶ千鳥を、目出度い物として格調高く歌っている。
15.夜雨節
*農民にとって夜の雨はありがたいもので、豊年の吉兆であった。祝儀歌としてよく歌われる。
16.仲筋ぬぬべーま節
*良質の苧麻の株を得るため、人身御供となって竹富島から新城島へ役人の妾にやられたヌベーマ。母親の悲嘆を歌った物語歌。
17.みるく節
*弥勒は中国から伝わった豊壌をもたらす神。祝い座の終わりに更なる幸を願って歌われ、幕引きとなるのである。