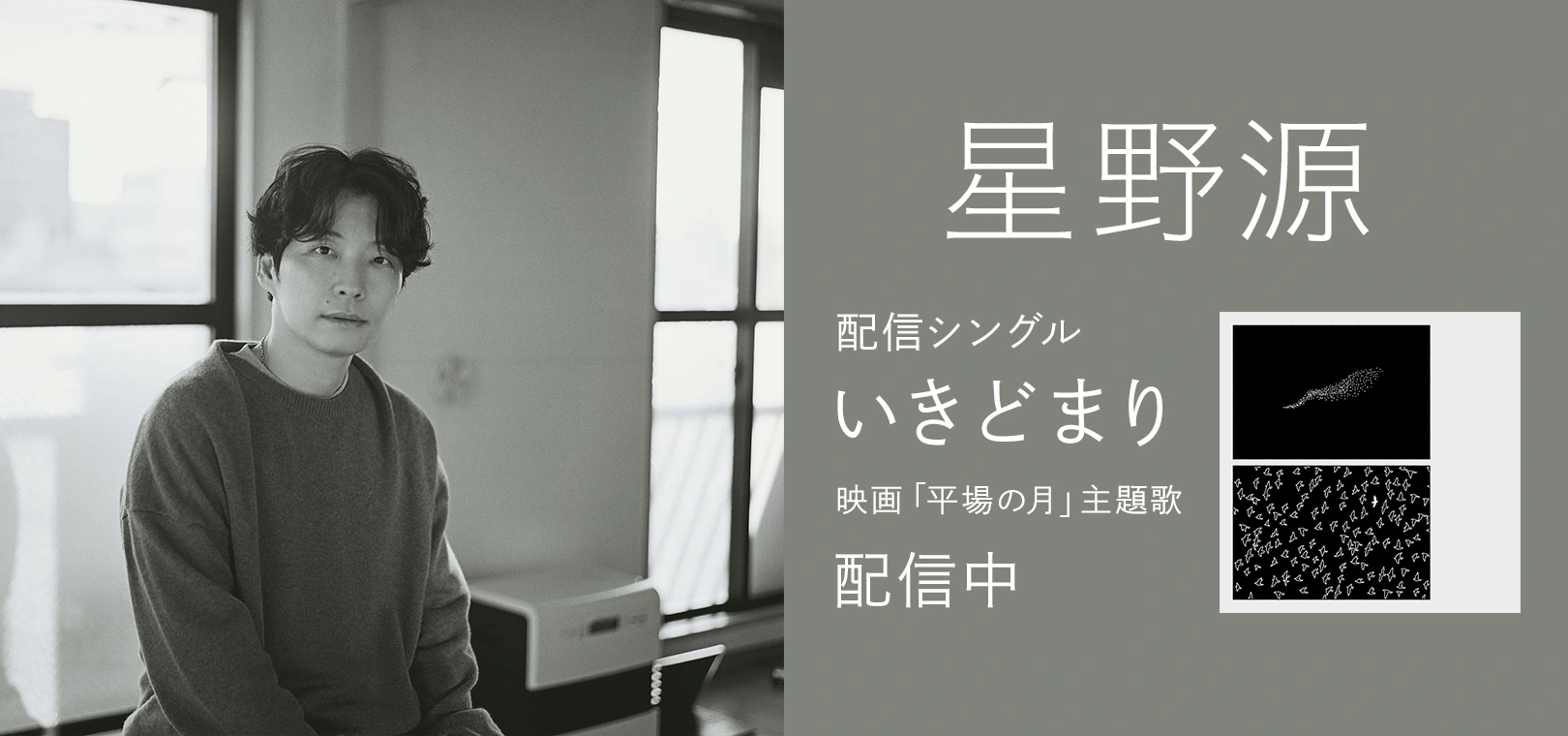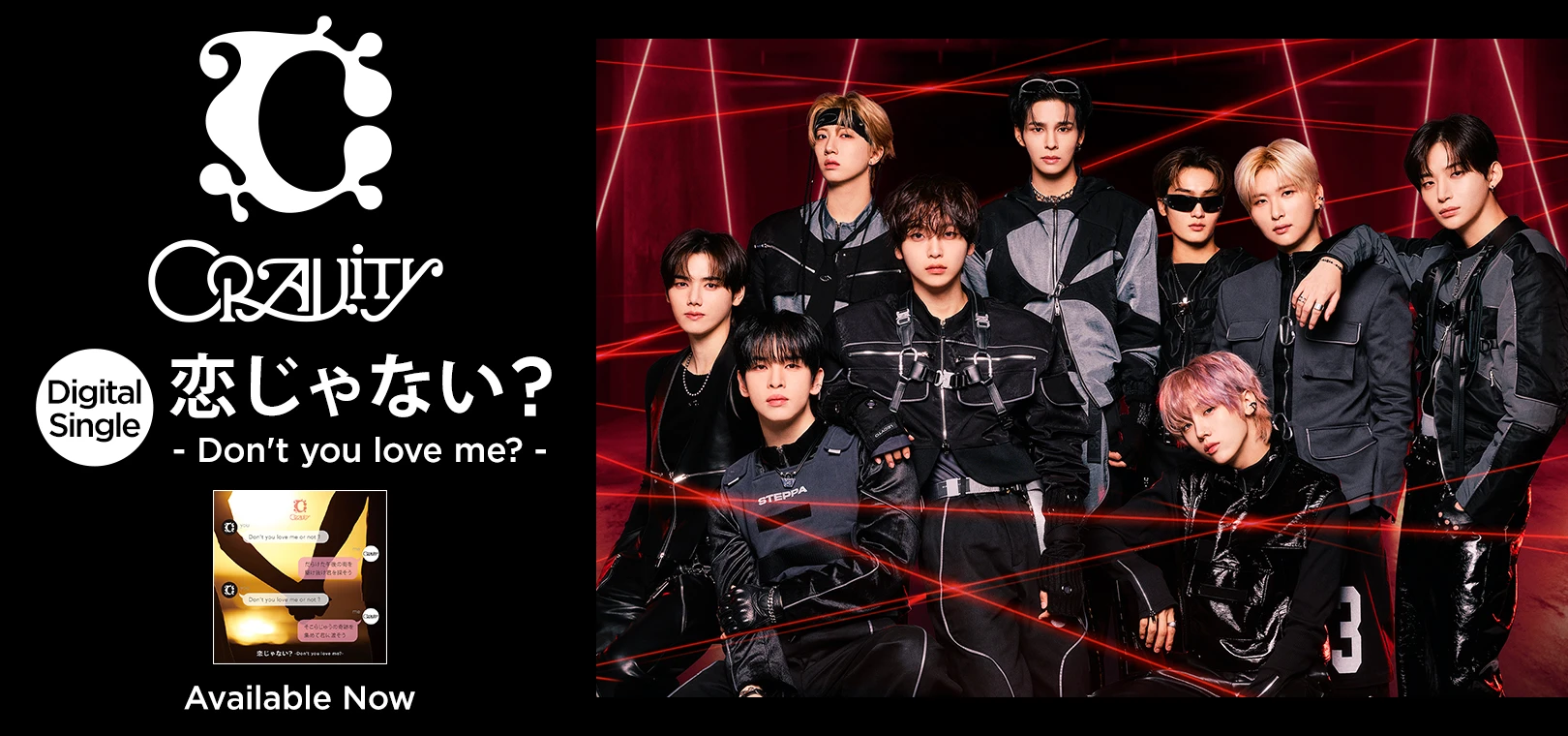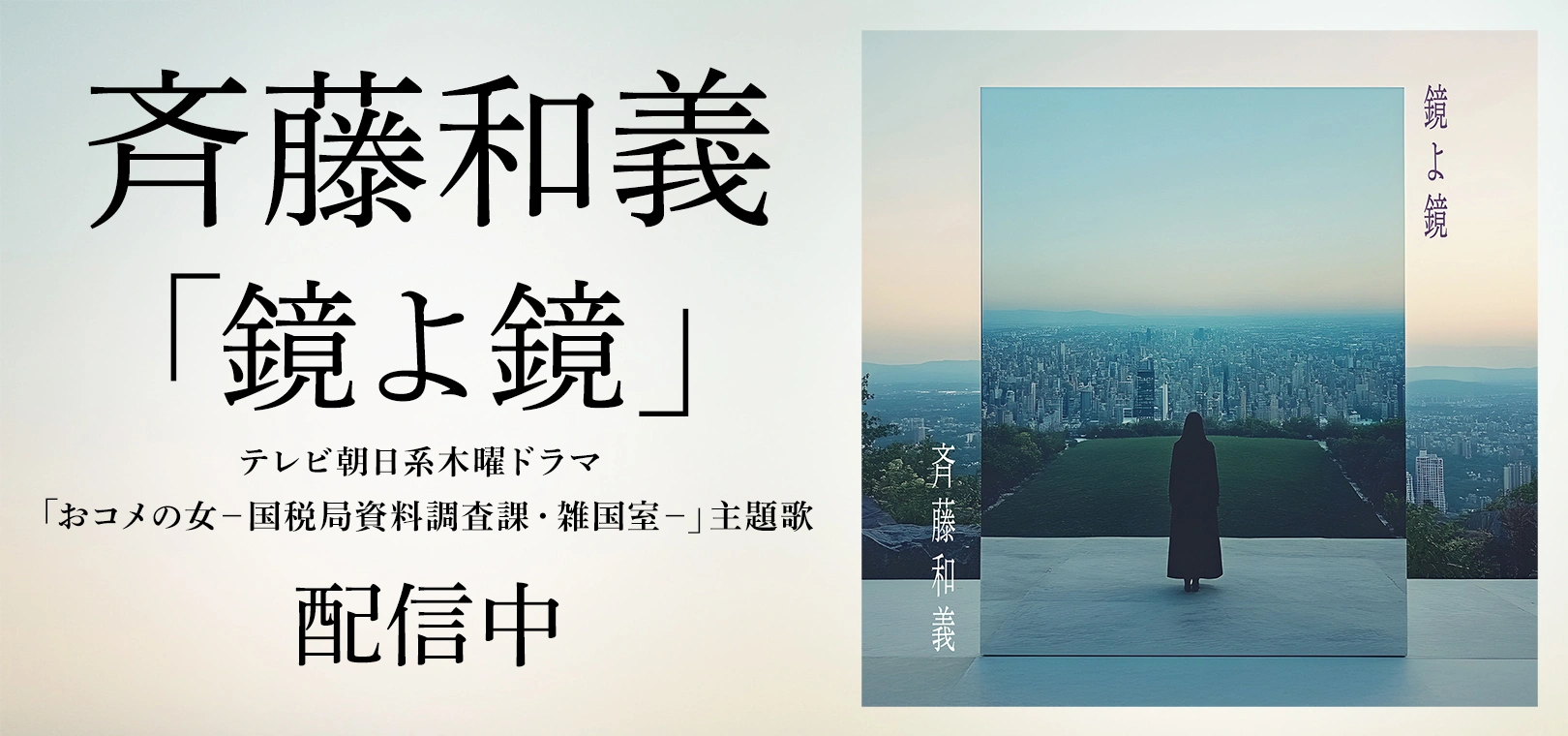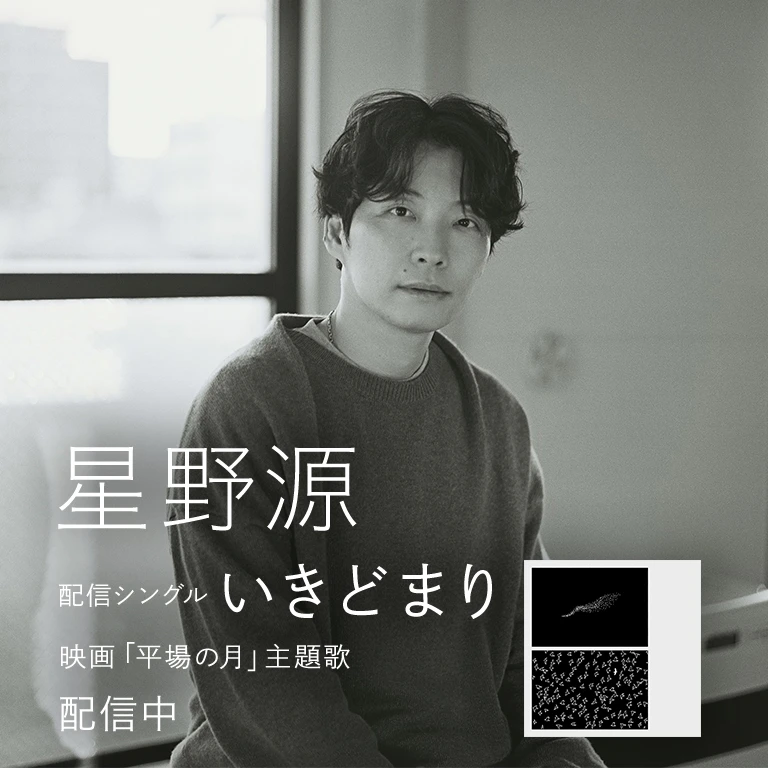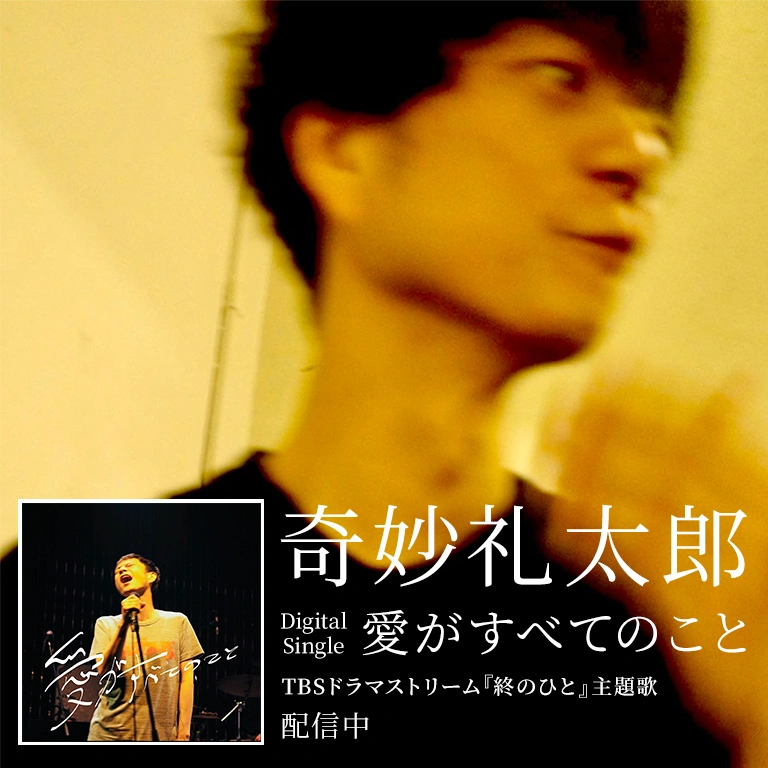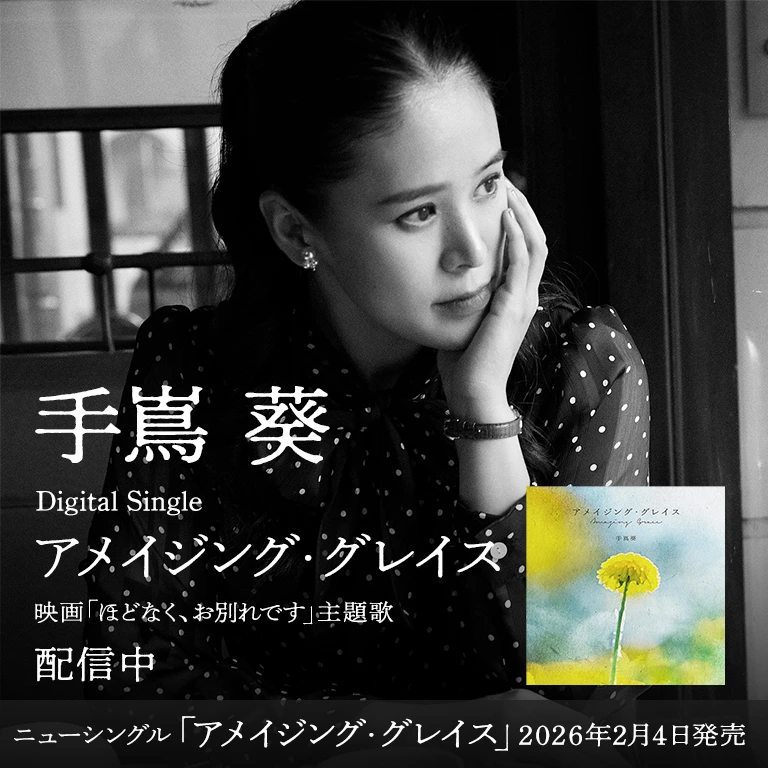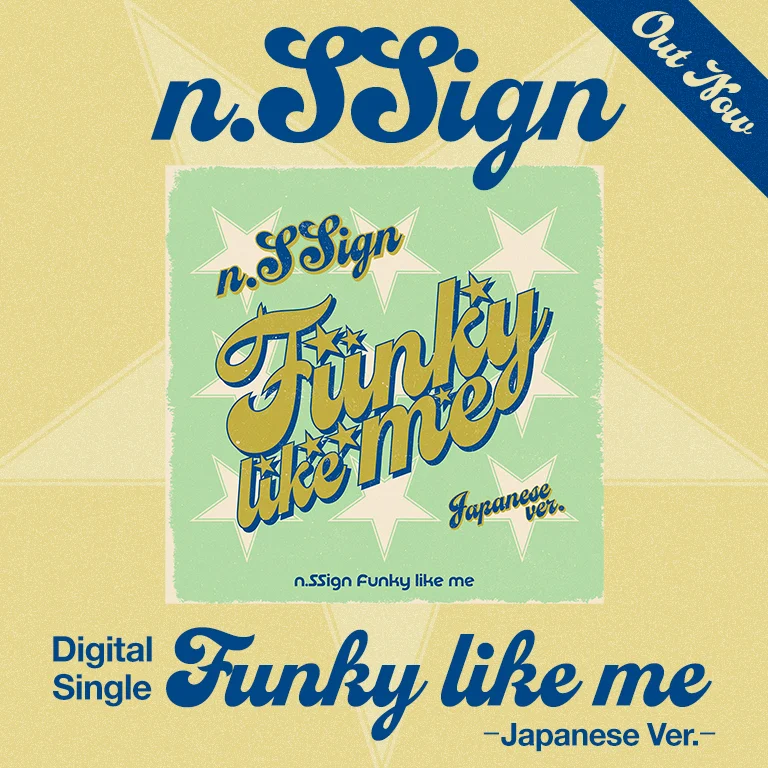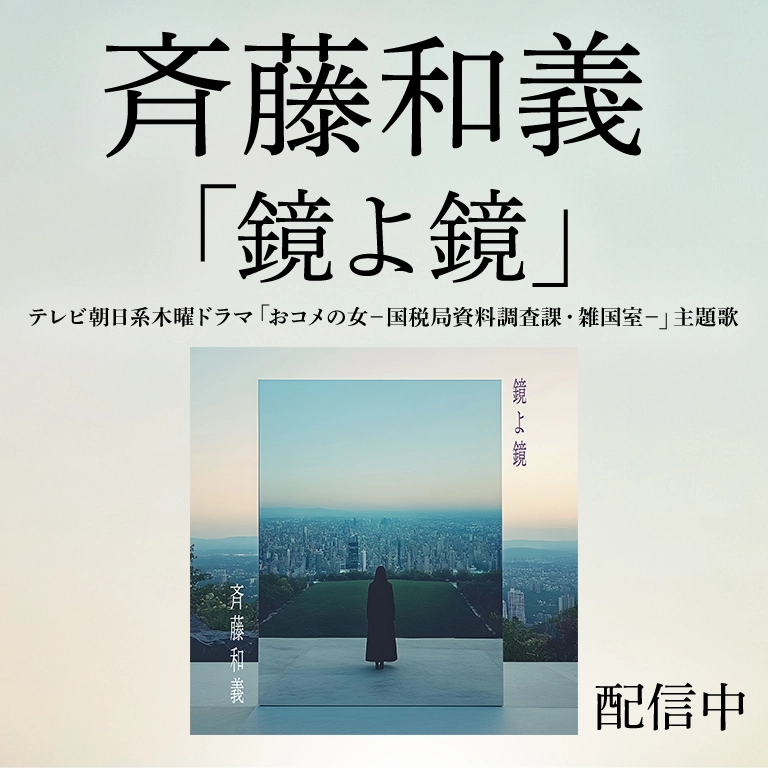須藤 千晴
CHIHARU SUDO
プレリュード
PRELUDES

-
01
第1番 ハ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.1 IN C MAJOR
-
02
第2番 イ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.2 IN A MINOR
-
03
第3番 ト長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.3 IN G MAJOR
-
04
第4番 ホ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.4 IN E MINOR
-
05
第5番 ニ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.5 IN D MAJOR
-
06
第6番 ロ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.6 IN B MINOR
-
07
第7番 イ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.7 IN A MAJOR
-
08
第8番 嬰ヘ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.8 IN F SHARP MINOR
-
09
第9番 ホ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.9 IN E MAJOR
-
10
第10番 嬰ハ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.10 IN C SHARP MINOR
-
11
第11番 ロ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.11 IN B MAJOR
-
12
第12番 嬰ト短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.12 IN G SHARP MINOR
-
13
第13番 嬰ヘ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.13 IN F SHARP MAJOR
-
14
第14番 変ホ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.14 IN E FLAT MINOR
-
15
第15番 変ニ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.15 IN D FLAT MAJOR"RAINDROP"
-
16
第16番 変ロ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.16 IN B FLAT MINOR
-
17
第17番 変イ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.17 IN A FLAT MAJOR
-
18
第18番 ヘ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.18 IN F MINOR
-
19
第19番 変ホ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.19 IN E FLAT MAJOR
-
20
第20番 ハ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.20 IN C MINOR
-
21
第21番 変ロ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.21 IN B FLAT MAJOR
-
22
第22番 ト短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.22 IN G MINOR
-
23
第23番 ヘ長調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.23 IN F MAJOR
-
24
第24番 ニ短調(ショパン:24の前奏曲 作品28) NO.24 IN D MINOR
-
25
第3番 ト長調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.3 IN G MAJOR
-
26
第4番 ホ短調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.4 IN E MINOR
-
27
第5番 ニ長調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.5 IN D MAJOR
-
28
第6番 ロ短調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.6 IN B MINOR
-
29
第7番 イ長調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.7 IN A MAJOR
-
30
第9番 ホ長調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.9 IN E MAJOR
-
31
第11番 ロ長調(スクリャービン:24の前奏曲 Op.11より) NO.11 IN B MAJOR
作品について 須藤 千晴(ライナーノーツより抜粋)
フレデリック・ショパン(1810~1849):24の前奏曲 作品28
近年では、そのメロディーの美しさから、ショパンの作品はノクターンなどを初めとして他の楽器でも頻繁に演奏されるようになり、更に多くの方に親しみを持たれるようになったことはとても嬉しいことですが、私自身忘れずにいつも敬意を評したいと思っていることは、ショパンがいつも「純粋なるピアニスティック」であるものに身を捧げたということです。ピアノという楽器の特徴を深く把握し、何度も何度も試行錯誤を繰り返した結果、信じられないほどに美しく繊細な装飾を多くの作品に施し、そして更には、例えばこの曲集第13番や第21番などにもみられると思いますが、ピアノを「声楽的」に歌わせることにも様々な工夫をこらし、この上なく美しい旋律をつくりあげたのです。
24の全ての調性を用い、長調と短調という2人の交わす会話のように、あるいは光と影、幸せと苦悩といった様な相反するものを、繊細かつ綿密に、まるで万華鏡のように織り成し、絶望の中から、きらめく様な美しさや生への喜びをも表現した、彼の精髄を残したショパンの最高傑作と言うことができます。
アレクサンドル・スクリャービン(1872~1915):24の前奏曲 作品11
ショパンやリストを敬愛していたスクリャービンは、ショパンがバッハに対してそうだった様に、ショパンの24の前奏曲に深く感銘と影響を受け、この作品を完成させました。
スクリャービンは1902年頃から哲学や神秘思想へ傾倒を深めていった為に、後期の作品には神秘和音や全音音階などが多用され、独自の響きが作り上げられましたが、16~24歳の間に作曲されたこの前奏曲集においては、ショパン同様5度圏に従った調性配列を用いて、その曲調もまた、ショパンに酷似しているものもあり、まだ過激なまでにはその自我が表れてはいない、激しくも清々しく溢れ出す情熱に満ちた、若い時代の佳作となっています。