 |
  |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
   |
|
 |
|
夜な夜な街に繰りだして収穫した音はどんな音なのか?私は気なって夜も眠れない日々が続いた。音楽に関しては私の専門外なので、血走った目を擦りながら、電話帳片手に音楽評論家に片っ端から連絡を取った。が、何故か皆一様に口を閉ざし、作業は難航した。鉛色の雲が空を覆うとある日の午後、目深に帽子を被った黒いコート姿の男が私の元に現れ、CUBE JUICEについて重い口を開いてくれた。彼の名は、沢田太陽氏 CUBE JUICEを良く知る数少ない音楽評論家の一人だ。
|
|
 |
 |
| 2002.4.21 マタチューケッツ大学 人類行動学研究学部 教授 |  | 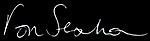 |
|
 |
 |
|
最近、邦楽アーティストたちの楽曲がこぞって洋楽”っぽく”なっている現象がハッキリと感じられる。パンクやオルタナ、R&Bにヒップホップ。こうしたタイプのサウンドはもはや日本の音楽シーンにおいても通常のフォーマットのものとなりつつある。こうした現象を見て、「もう日本の音楽レベルは海外に追い付いた」だの「日本の方が洋楽より面白い」だのと発言している人たちも、僕は随分と知っている。だが、そうした言葉を聞く度に、僕は「本気か?」と首をひねってしまう。考えてもみてほしい。オルタナにせよパンクにせよ、R&B/ヒップホップにせよ、90年代の前半には欧米では既に定着していた音楽である。日本は海外から約10年近く遅れてようやく欧米のそうしたモードに追い付きつつあるというのに過ぎないのである。そうした”油断”からか、最近の日本の、特にオルタナティヴ・ロック系の楽曲がことごとくつまらないものになってきている。それは極度に従来のJ-Pop調に歌謡曲化したものか、単なる流行り洋楽のまんまコピーか、あるいは欧米の現地の人でもよく知らないような”先鋭的”というふれこみだけのやたらと難しい前衛なだけのロックに手を出してワケわからなくなってるか。そうしたものが大半を占めるようになっている。では一体何故にそうした現象が起こってしまうのか。
それはズバリ今の日本が、欧米で実際のところ主流となっている音を聞き逃してしまっているからだ。今の欧米で実際に熱い音というのはどういうものか。それは”エクレクティックなポップ・センス”。エクレクティック。つまり、“いろんなものを混ぜ合わせた”という意味なのだが、もはや今の世界の音楽シーンの主流は上にあげたようなオルタナもテクノもフォークのような歌ものもヒップホップも一切合切融合して当たり前のものとなっているのだ。ティンバランドがドラムン・ベース風のブレイク・ビーツをマシーナリーなチキチキ・ビートに改良しヒップホップ界を変革してから既に4年。今やそうしたビートはスーパー・ファーリー・アニマルズのようなUKロックのアーティストやネリー・ファータドやデヴィッド・グレイのようなシンガーソングライターの楽曲のリズムに普通にかつ自然に導入されるようになっている。またテクノの側にしてもモービーのようにバンド編成でライブをし、ロックやアメリカン・ルーツ・ミュージックの要素を混ぜたりすることももはや決して珍しいことではない。何?アーティストの名前に聞き馴染みがない?いずれも本国じゃトップクラスの大物アーティストなのだがなあ…。では、こういう比喩ではどうだろう。レディオヘッドやビヨークが密室性の高い先鋭的なエレクトロニカを導入しロック界に衝撃を投げかけ、R&Bの世界ではジャズや70'sのソウルにヒップホップの要素を融合した、ディアンジェロに端を発する”オーガニック・ソウル”と呼ばれる生感覚のR&Bが今や一大主流となるつつあること。こうしたことを例に出すと、今の本場の音楽シーンがジャンルはもとより時代性をも超越した音楽性を混合して融解し、独自な音楽を刻々と作り上げているかはわかっていただけるだろう。それに比べて日本は多少の例外を除いて、大概の場合が「ロック」「R&B」「テクノ」といったジャンルの固定観念に縛られたまま。ロックのリズムは相変わらず平板だし、テクノやR&Bも表情に乏しいものが多く見受けられる。厳しい言い方だが、これは紛れもない事実である。そうした生温い中途半端な洋楽“もどき”な音が日本で溢れかえる中、こうした今の欧米のリアルな動きにきちんと自分なりの返答を示した日本人アーティストがここに登場した。
その名はCube Juice。27歳になったばかりの男性シンガーソングライター、長尾伸一によるひとり宅録ユニットだ。そういうとイメージ的にはコーネリアスや中村一義のイメージを思い浮かべるかもしれない。確かに彼が99年にインディでデビューした当時は、そうした印象をもたれてもしょうがない雰囲気は正直なところあった。僕は彼自身の音源を2000年の春頃にはじめて聴いているが、そのときの彼はまだ、彼が敬愛するビートルズや90'sのパワー・ポップ系のアーティストを意識したかのような、いかにも90'sのオルタナティヴ・ロックなサウンド・アプローチを展開していた。その作品のクオリティ自身は悪くなかったものの、西暦2000年というタイミングでは既にそうしたタイプの楽曲は世にいくつも出されていた。彼のビートルズに対しての敬愛ぶりは理解できるが、日々刻々と移り変わるポップ・ミュージックの流れに対し、どうも歩調を合わせ切れていないような、そうしたもどかしさを当時の彼に僕は感じていた。
しかし、チキチキ系のデジタル・ビートとの出会いで、現在におけるリズムの重要性やエクレクティックな感性に目覚めて、Cube Juiceの音楽は劇的に変わった。今の彼は、一小節ごとにどんなノイズやブレイクビーツが入ってくるのかわからない意外性に満ちた迷宮のようなポップ・ワールドを展開させることが可能になった。これはただでさえ、現在の日本のシーンにおいては飛び抜けて異端な音。ただ、そうした複雑な展開を次々と繰り出す事はややもすると難解な印象を与えかねないのだが、Cube Juiceはそうした課題を、彼が本来持っていたビートルズの影響を覗かせる類い稀なポップ・センスを発揮することで絶妙に折り合いをつけ、実に彼らしい「2002年の音」を作るのに成功している。
「実験的にしてかつ普遍的」。Cube Juiceはビートルズの時代以来ポップ・ミュージックの普遍的な理想となっている命題に勇敢にトライするようになってきた。勿論、現時点ではまだまだ課題は多い。歌唱力の部分でもうちょっとアピールできる説得力は欲しいし、複雑なリズムのコントロールの仕方もまだまだラフな部分も見受けられる。おそらく、今ビートルズが存在していたならば、同じアプローチをとるにせよ今の彼の数10倍はクールにキメてくれるとは思う。しかし、今はまだそれでいい。ここ最近の日本のオルタナティヴ系のアーティストがどこかに置き忘れてきた、「欧米の最新モードに対する日本なりの回答」を見い出そうともがいているその姿だけでも大いに賞賛に値するのだから。
Cube Juiceが繰り出すこうしたサウンドに驚きを覚えるリスナーはこれからきっと数多く出てくることだろう。そして、やたらとジャンルづけをしたがる日本人の特性から「これは何系なの?」という声もあがるだろう。まあ、あえて言うなら先程から何度か使った“エクレクティック・ポップ”というのがある程度は適切なのだが、Cube Juiceの音楽にそうした固定した冠を被せる必要は一切ない。 “2002年型ポップス”。ズバリ、それで良い。これこそが今の世界で鳴らされていて当然の音なのだから。
沢田太陽
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
| (c) TGB DESIGN |
| Copyright(c)2002 Victor Entertainment, Inc. All rights reserved. |
 |
 |
|
 |
|
 |