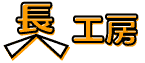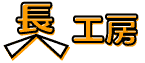| (幻の迷?作ここに公開) |
 |
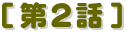 |
グッド・モーニング・エブリバディ!いやぁ、すがすがしい朝だね。ん?みんな何してんの。もうとっくにレコーディング始まってると思ってたのに�。」
鏡 弘明 56才 長沢涼子のプロデューサー。昨年まで大手レコード会社 日本コロンブスレコードの制作部長だったが、突然退社しフリーのプロデューサーになって最初に手掛けたのが、長沢涼子だった。昔は「演歌といえば鏡」と言われるほど、業界で有名な演歌のプロデューサーであった。無論現在もこの鏡のおかげで長沢涼子が成功したといっても過言ではなかった。
ディレクターの藤井が振り向きながら、
「もう信じられまへんわ�昨日の晩あれだけ飲んでて、ようそんな元気で起きて来はりますねぇ。ちょうど今からはじめるところなんですけど、今いっちゃんに志村君呼びに行ってもらったんですよ。」
「志村君まだ起きてこないの、ちょっとたるんでるんじゃない?社長が知ったらまたいつもの『馬鹿やろう志村、このやろう!』が始まっちゃうぞ。」
「それじゃあ鏡さん、志村君ほっといてそろそろ始めましょうか。涼子ちゃん!スタンバイよろしく。」
「はぁーい、今日は『夢ほおずき』からですよね。」
「村田さん、すぐ音でます?」
「大丈夫、だんだんバランス取っていくから�。」
村田雅夫 35才 ビスターレコードのミキサー。長沢涼子が演歌に変わってからはチーフ・エンジニア 村田雅夫、アシスタント・エンジニア 矢崎良江 23才というコンビが担当していた。
「志村さん!」
一子は床にうつぶせに倒れている志村の身体を揺さぶったが、反応はなく肌は冷えきっていた。 - 死んでる�。一瞬金縛り状態になったが、しばらくして気を取り戻した一子は、志村が右手に握っているものに気がついた。 - 譜面?のような紙の切れ端だった。とっさに彼女は取り上げて自分のポケットにしのばせた。部屋の周りを見渡して、他に変化がないことを確認して警察に通報したが、それは自分でも驚くほど冷静だった。
すでに地元警察による捜査が進み、被害者の死因は青酸性の毒物による服毒死と判明、現場の状況から他殺の線が濃厚とみられた。
しばらくして、山梨県警の樋口警部と渡部刑事が到着した。
「警部、一度でいいからこんなスタジオで歌ってみたいですねぇ。」
「なべさん、馬鹿なこと言ってないでスタジオにいた関係者を集めてくれないか。」
「はい、すでにロビーに全員集まってもらっています。被害者は志村恭人 31才 バイキング・プロダクションの社員で、警部もよくご存知の演歌歌手、長沢涼子のマネージャーです。かなりのやり手だったらしく、被害者に恨みをもっている人間は大勢いるようですね。」
スタジオ・ロビーに集められた関係者は次の8名だった。
北浦一子(29) 長沢涼子の友人
長沢涼子(25) 演歌歌手
鏡 弘明(56) プロデューサー
藤井 武(33) ディレクター
与田隆士(32) プロモーター
林田雅夫(35) ミキサー
矢崎良江(23) アシスタント
仲谷康男(32) 運転手
このうち村田雅夫と矢崎良江が別棟のエンジニア用のコテージに泊まり、その他は全員同じ宿泊ロッジに泊まっていた。
「警部、この山中湖スタジオの立地条件からして、外部から侵入しての殺害ということは考えられませんね。」
「うむ、死体の状況から、恐らく死亡推定時刻は今日7月27日の午前3時から5時くらいだろうな。」
「ちょうど『歌うヘッドライト』のやってる時間ですね。私、たまに酔っ払いながら聴いているんですよ。」
「なべさん、馬鹿なこと言ってないで、早く一人ずつ話を聴いてみようじゃないか。」
「はい、それでは第一発見者の北浦一子から宿泊ロッジのロビーに来てもらいます。」
一子はせきを切るようにしゃべり出した。
「私が志村さんの部屋へ行ったとき、鍵が開いたままになっていたんで中に入ると、ベッドの横にうつぶせに倒れている志村さんが見えたんです。声をかけても返事がないし、手が冷たくなっていたんで、もうびっくりしてすぐに110番したんです。」
樋口警部は、一子にまあ落ち着きなさいというやさしい目で、
「部屋の中で何か変に思ったことはありませんでしたか?」
「私、気が動転していて、何がなんだかあんまり覚えてないんです。」
「わかりました。それでは亡くなった志村さんはどんな方でしたか?」
「涼子ちゃんのマネージャーということだけで、特別親しくしていたわけじゃないから、よく解らないけど、お酒を飲むと普段とぜんぜん変わってめちゃくちゃ明るくなるんですよ。」
「普段はよっぽど暗かったんですか?」
「そういうわけじゃないけど、仕事に大変厳しい人だったから�。」
「志村さんが誰かに恨みを買っていたということはありませんか?」
「それだったら、私より涼子ちゃんのほうがよく知っていると思います。」
一子はこのときばかりはしっかりと答えたが、その様子に樋口警部の眼鏡がキラリと光った。
*この物語はフィクションであり実在の人物・会社等とは一切関係ございません。
|
|