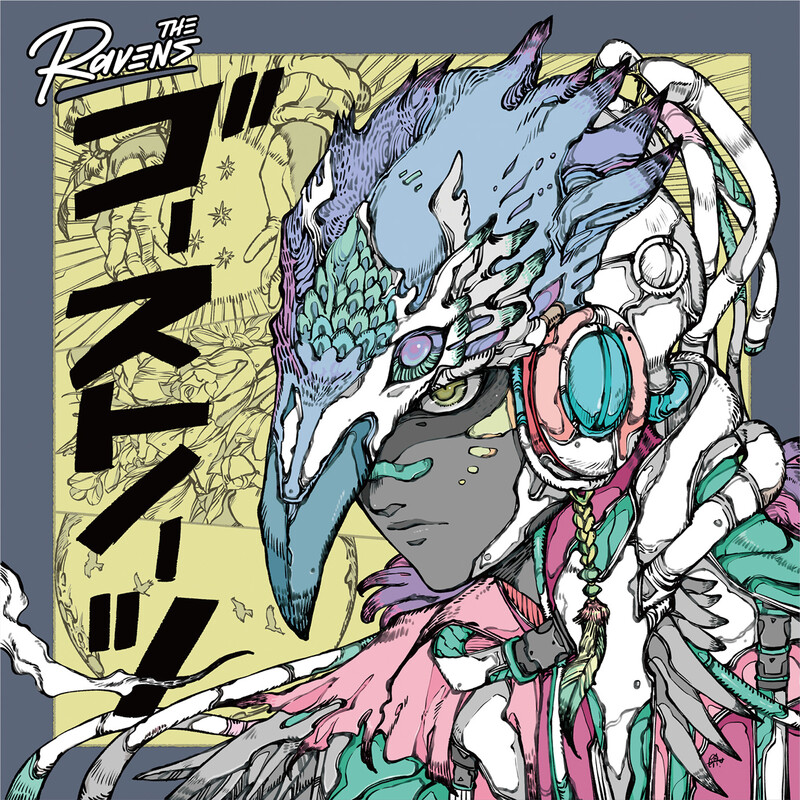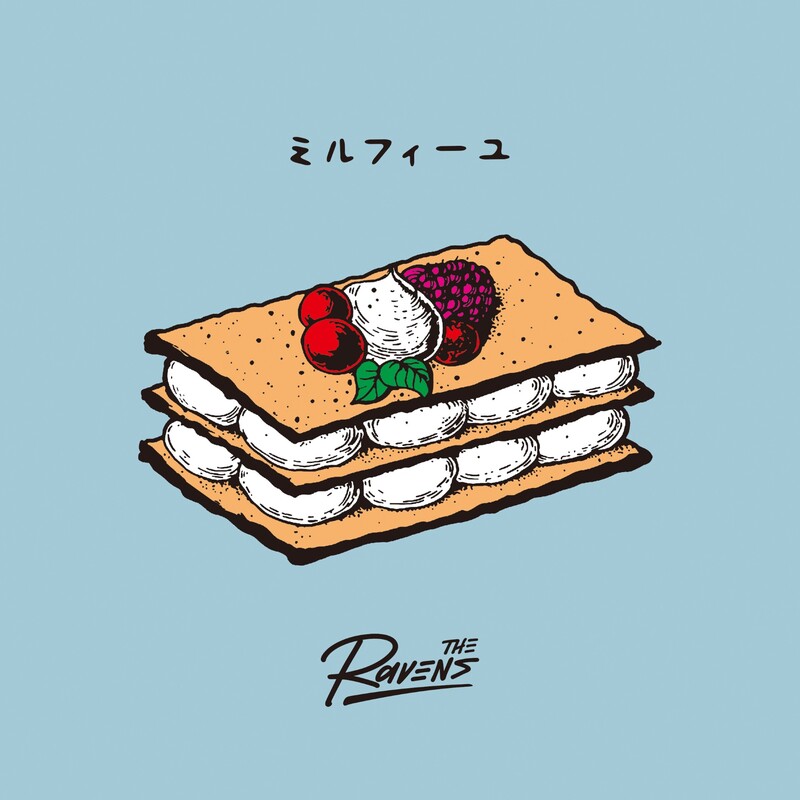The Ravens
The Ravens
NEWS
ニュース
2022.08.31
1stアルバム『ANTHEMICS』オフィシャルインタビュー
Kj(Vo・G Dragon Ash)、PABLO(G Pay money To my Pain/POLPO/REDORCA)、武史(B 山嵐/OZROSAURUS)、渡辺シュンスケ(Key Schroeder-Headz)、そして櫻井誠(Dr Dragon Ash/ATOM ON SPHERE)という、ロックバンド界屈指の猛者4名と天性のピアノマンによって結成された5人組バンド「The Ravens」。そのファーストアルバム『ANTHEMICS』が遂にリリースされた。
The Ravensはそもそも、Kjが降谷建志名義でドロップした、作編曲のみならずKj自身がすべての楽器演奏までを手がけた『Everything Becomes The Music』(2015年)、『THE PENDULUM』(2018年)という2作のアルバムをライブで表現するために集ったところから始まっている。この5人での初ライブは2015年6月、『Everything Becomes The Music』のリリース日にビクタースタジオから生配信で行われたスタジオライブ。当時はまだ名もなき集団だったが、2018年に夏フェス等に出演、さらには秋にソロファーストツアーを回るにあたって「Kj and The Ravens」という名が掲げられ、その数々のライブ&ツアーで得た手応えと充実がそのまま正式なバンド発足へと繋がっていった。
「元々このバンドは、インプロ(インプロビゼーション=即興演奏)を凄いやってたんだよね。敢えて曲数を少なめにしてインプロの時間を無限に取るくらいの勢いでライブをやってたんだけどさ、そうやって5人で自由にやるインプロが超カッコよくて。これをもっとちゃんと音楽にしたい、作品として封じ込めたいっていう想いもあった。当時から俺はバンドのつもりでやってたけど、とはいえ俺のソロプロジェクトではあるから、そうするとどうしても最終的に『建志がやりたいことでいいんじゃない?』っていうジャッジになるわけじゃん。そうじゃない、もっと踏み込んだ形でこの5人で一緒に音楽をやれたらすげぇ楽しいんじゃねえかなって」
「ソロプロジェクトとして全部の楽器を自分で弾いて、完全に自分の思い通りのアルバムを2作完成させた時に、想像してたより満足しなかったんだよね。それで、自分が思い描いた通りに物事がまかり通っていくのってそんなに楽しくないんだなってことに気づいて。自分の感性の中だけにいることって音楽家としてそんなに幸福じゃないんだなというかさ。結局、自分のイメージ通りに行かないこと、自分のイメージとそぐわないことが起きていくのが面白いんだなっていうことがやっとわかった。……心象風景って自分の中から生み出されてると思いきや、他者からの影響を多分に受けて、それと自分の感覚がフュージョンして俺の心象風景になってるわけじゃん。だからそもそも俺の世界観を体現するのって、ひとりではできないものなんだなとも思ったし。それはソロをやる前にはわからなかったことだった」(Kj)
そして、5人は「バンド」として決意を新たにスタートを切り、まずは『モンスターストライク』の7周年に際して書き下ろした“Golden Angle”を制作。その後、本格的に今回のアルバム制作へと向かっていった。
「ライブではこのバンドで音を出した経験はあるけど、この5人で1から音楽を作るっていうことはやっていなかったので、どういうものになるのかというイメージとかは全然なかったんですよ。だから本当に手探りだったし、逆に、自分が出したものに対してみんながどんなものを投げ返してくるんだろうっていうのが楽しみで。実際、やればやるほどアンサンブルもどんどん変わっていくという、それは制作を重ねていく中で凄く感じましたね」(渡辺シュンスケ)
「改めて振り返ってみると、童心に返ってみんなで砂場で遊びながら作っていった感じがめちゃくちゃあって。もちろん、みんなそれぞれ自分の経験から『こうやったほうがいいだろうな』っていう知恵はあるんだけど、感覚としては鳴ってるものに対して頭の中に浮かんだイメージをただただ乗せていく――それは時には曲が元々イメージしていたものをひっくり返すようなものだったかもしれないけど、でも自分のバンドだし、とにかく自分が弾きたいものを弾こうっていう感覚で臨んだんですよね。それはきっと俺だけじゃなく、本当にみんな好き勝手、子供に返って自由に遊んでやってみようぜっていう中でできたアルバムだという感じがする。だからこそイビツな部分もあるけど、それが逆に、ある種の方法論が確立している今の時代だからこそよかったなとも思うし、僕らの世代のルーツミュージックとしての音楽の成り立ちに近いものもあるんじゃないかな」(PABLO)
この暗がりを超えて遥かなる夜明けと解放へと向かっていくかのような、雄大で美しい宣誓たる“Opening Ceremony”から始まる全12曲。Kjが作曲した8曲に加え、PABLO、渡辺がそれぞれ2曲ずつ書き下ろした楽曲群は、どれも一貫してソングライティングのクオリティが非常に高いのはもちろんだが、何よりもまず、極めて緻密であると同時に極めて自由でダイナミックな、そのバンドアンサンブルに驚かされる。5人のプレイヤビリティが遺憾なく発揮された“楽園狂想曲”に象徴的だが、歴戦の手練れたるミュージシャン達がいまだ少年のようにその胸に瑞々しく溢れ続ける音楽に対する好奇心を全開にし、互いが奏でる旋律やアイディアに触発されながら、各々がこれまでの音楽人生の中で培ってきたスキルを挑戦的に注ぎ込み、とても純度高くThe Ravensという音楽へと落とし込んでいる様は圧巻。紛うことなきバンドサウンドでありながらオーケストラサウンドのようなスケールと深みを湛えた響きが、Kjが綴り歌うメッセージと相まって、果てなき冒険譚をゆくような壮大で感動的な音楽体験をもたらす素晴らしいアルバムだ。
「俺にとっては今までに経験したことがないような曲達だったから、毎回『凄っ!』みたいな感じの連続だったんですけど(笑)。それについてくのは刺激になったし、自分のプレイとしても楽しかったですね。完成したものを聴いても、5人だし楽器の数は少ないんですけど、それ以上にいろんなものが聴こえてくる、それこそオーケストラのように聴こえる。そういう、今までにあんまり体験したことのない凄みを感じてます」(武史)
「The Ravensの曲は割と自由に解釈できる余白が多いんだよね。最初はそこに戸惑ってた部分もあるかもしれない。でも、その真っ白なキャンバスの上でいかに遊べるかを考えて自由にやっていったら本当に楽しくて。だから俺の中で溜め込んでたフレーズを出した部分もあるし、いろんな音楽を聴いていいなと思ったやつを取り入れた部分もあるし……そういう意味で、音作りも含めて自分の技術も向上したし、ドラミングの多様性をより深く表現できたんじゃないかと思う。だから自分でもわかるぐらい、1曲作り上げるごとにスキルが上がってるなって思った。今まで音楽に対してあぐらをかいてたわけでは決してないし、常に真剣にはやってるんだけど、こうやって別のアプローチでまた新たに音楽に向き合うと、まだまだこんなに成長できるんだと思えた。それは凄く楽しかったし、学びが多かったですね」(櫻井)
「コロナ禍で始まったということに尽きると思うんですけど、ライヴもできなくなって、気軽に集まって音を出すことも人と飲みに行ったりすることもできない中で、リモートというスタイルでレコーディングが始まって………だから最初はどうなるんだろう?って思いながらだったんですけど、できていくものを聴いていったら、コロナ禍で今までやってたことが当たり前じゃなくなった中で感じてたことやいろんなもどかしさ含め、みんなの想いが溢れてるなっていうのを強く感じて」(渡辺)
パンデミックによる行動制限が始まった直後から制作が開始され、全編リモートレコーディング――つまりは作曲者のデモをベースにそれぞれが自身のフレーズを考え、一人ひとり音を紡ぎ重ね、次のメンバーへとバトンを渡していくという形で生み出された本作は、必然的に、コロナ禍という先の見えない日々の中で彼ら5人がその日々と己の人生に向かい合い、この2年をどうやって生きてきたのかを映し出すドキュメントとしての性質も持ち合わせている。PABLO作曲の“Never Come Back”以外は敢えてすべて日本語詞で綴られた、Kjのディスコグラフィの中でもDragon Ash最初期以来となるリリックのスタイルは自ずとここに託された想いの強さを想起させられるのだけど、どの曲もとてもリアルで切実なメッセージに満ちている。時に心の奥底を真っ直ぐに見つめるように語りかけ、そして時にどこまでも天高く飛翔してゆく開放的なメロディも然り。自分の意思とは関係なく不条理に揺れ動く人生の脆さ儚さ、不確かさに足元を掬われそうな不安も偽りなく吐露しながらも、それでも胸の奥にある光を決して絶やすことなく今を生きることで明日を切り開こうとする――その狂おしいほどの願いと衝動を音楽をもって肯定する、まさに讃美歌=Anthemicsのようなアルバムでもある。
「このアルバム自体が、本当に超大切な活動記録になったと思う。一番最初に作ったのは“Anthemic”っていう曲なんだけど、その曲で<奈落に喝采を>って歌っていて。コロナ禍になってライヴもできなくなって、あの頃の俺達は本当に奈落の底にいたから。それでも<奈落に喝采を>と歌って、そこから5人でこのアルバムを作っていって。その上で、最後に作った“XOXO”という曲で<こんな日々も悪くは無いかな>って歌えた――それは俺にとって本当に素敵なことだった。コロナ禍の中で俺らもみんなと同じようにイライラしてたし、言ってみればバンドマンはみんなと同じかそれ以上に食らっちゃってたところもあったと思うんだよ。『俺は何やってんだろう?』みたいなさ、社会から取り残された感覚もあったし、もどかしさを感じてた部分もあったから。でも、そんな日々の中でこのメンバーと一緒にこの作品を作ったことによって、最終的に<こんな日々も悪くは無いかな>っていう言葉が素直に出てきたくらい、このアルバムの制作が充実してた。もちろんこんな状況にならないほうが絶対によかったけど、でも『ANTHEMICS』を作れたことで、もしかしたらこの期間も悪くなかったんじゃないかって言えるところまでこの期間の自分達を肯定できた。それが俺にとっては一番大きな財産かな」(Kj)
The Ravensのファーストアルバム『ANTHEMICS』。彼ら5人がこの日々の中から揺るぎない輝きを生み出した本作は、今この時、あるいはいつかの未来で、この不確かな世界の中で惑いながらも生きる誰かの心に確かな光を灯すだろう。
有泉智子(MUSICA編集長)
■リリース情報
The Ravens
1st ALBUM「ANTHEMICS」
2022.8.31 OUT
The Ravens『ANTHEMICS』
2022年8月31日発売
生産限定盤 (CD+DVD)VIZL-2089 / 税込\4,180 [ BUY ]
通常盤(CD)VICL-65722 / 税込\3,080 [ BUY ]
ビクターオンラインストア限定セット(CD+DVD+ソックス)NZY-10005 税込6,930円 [ BUY ]