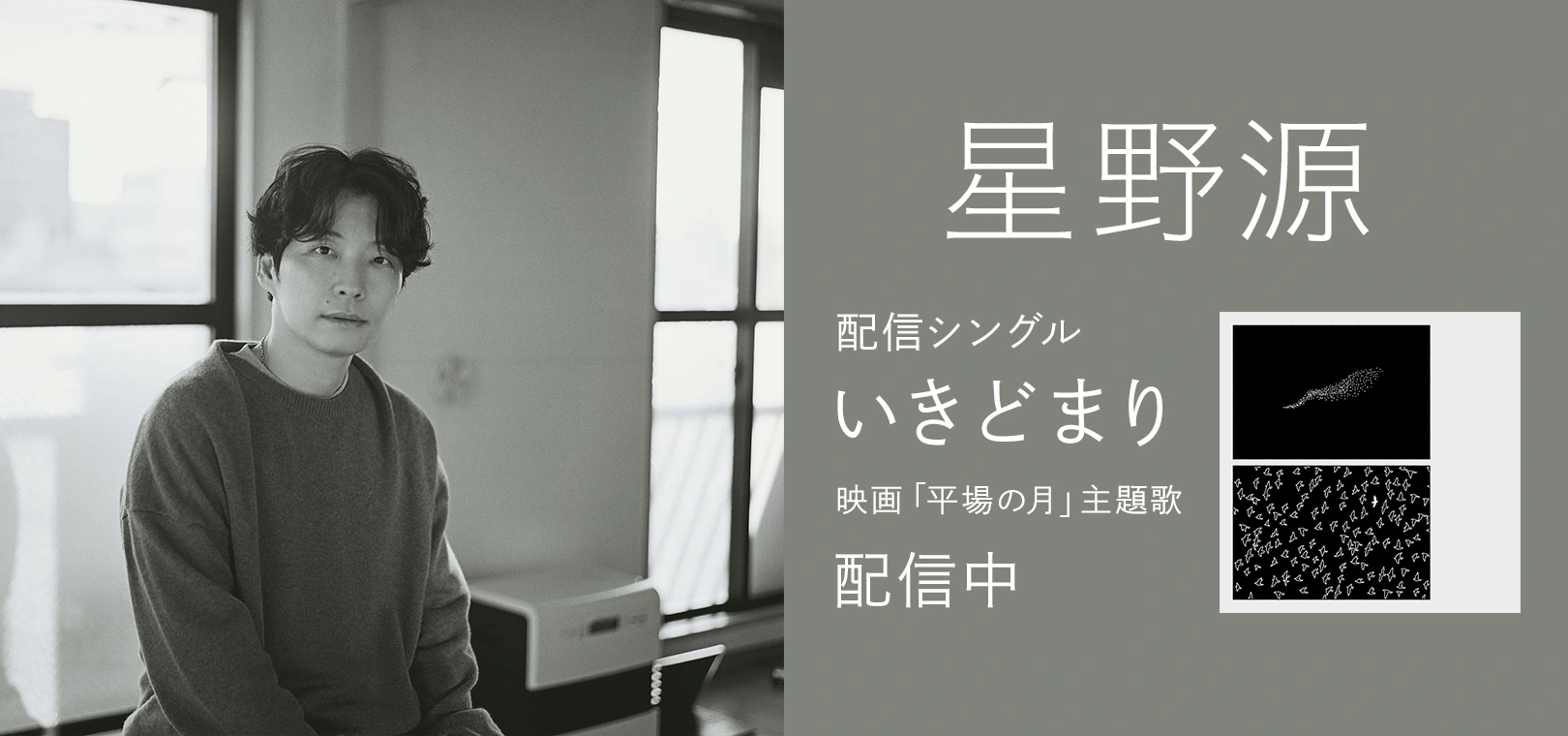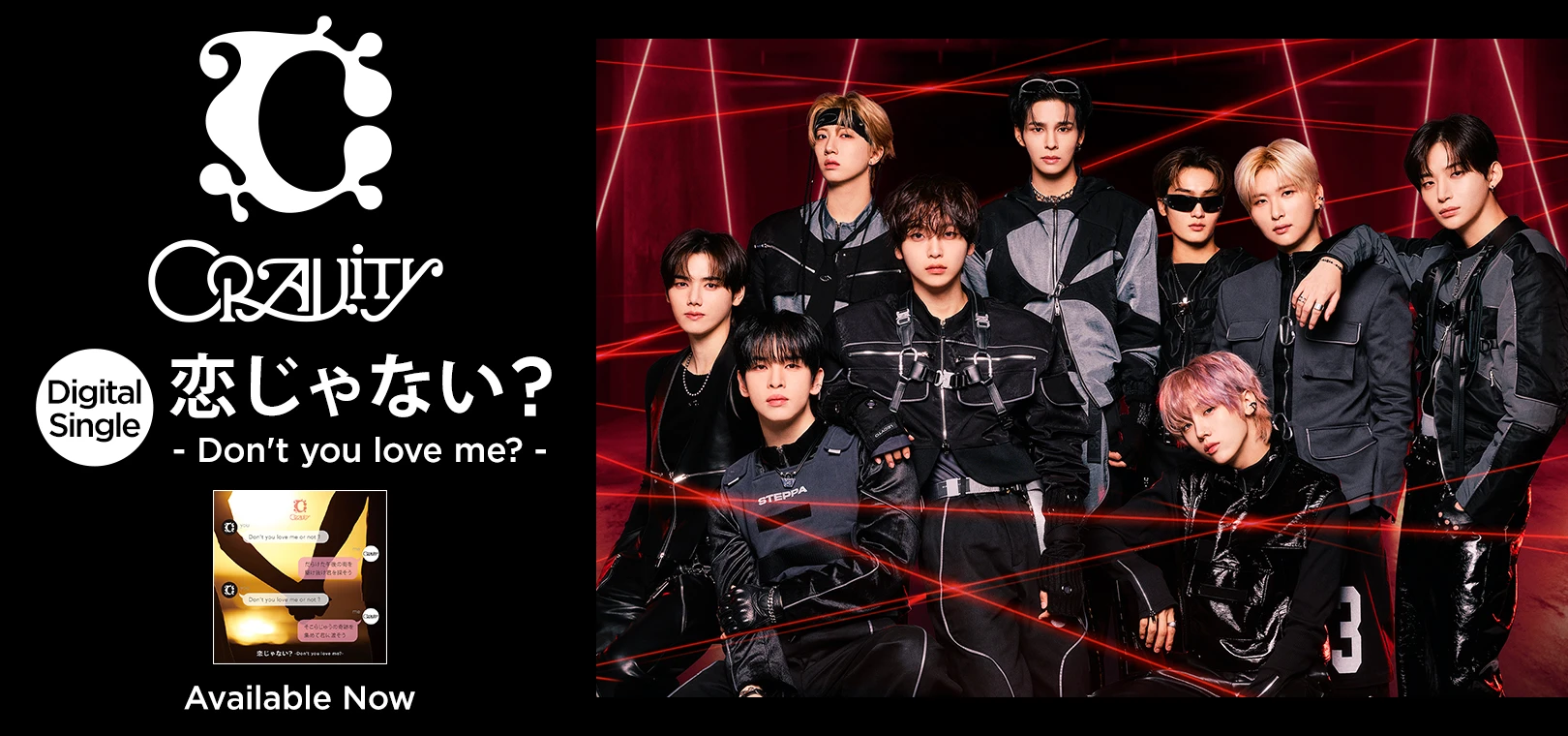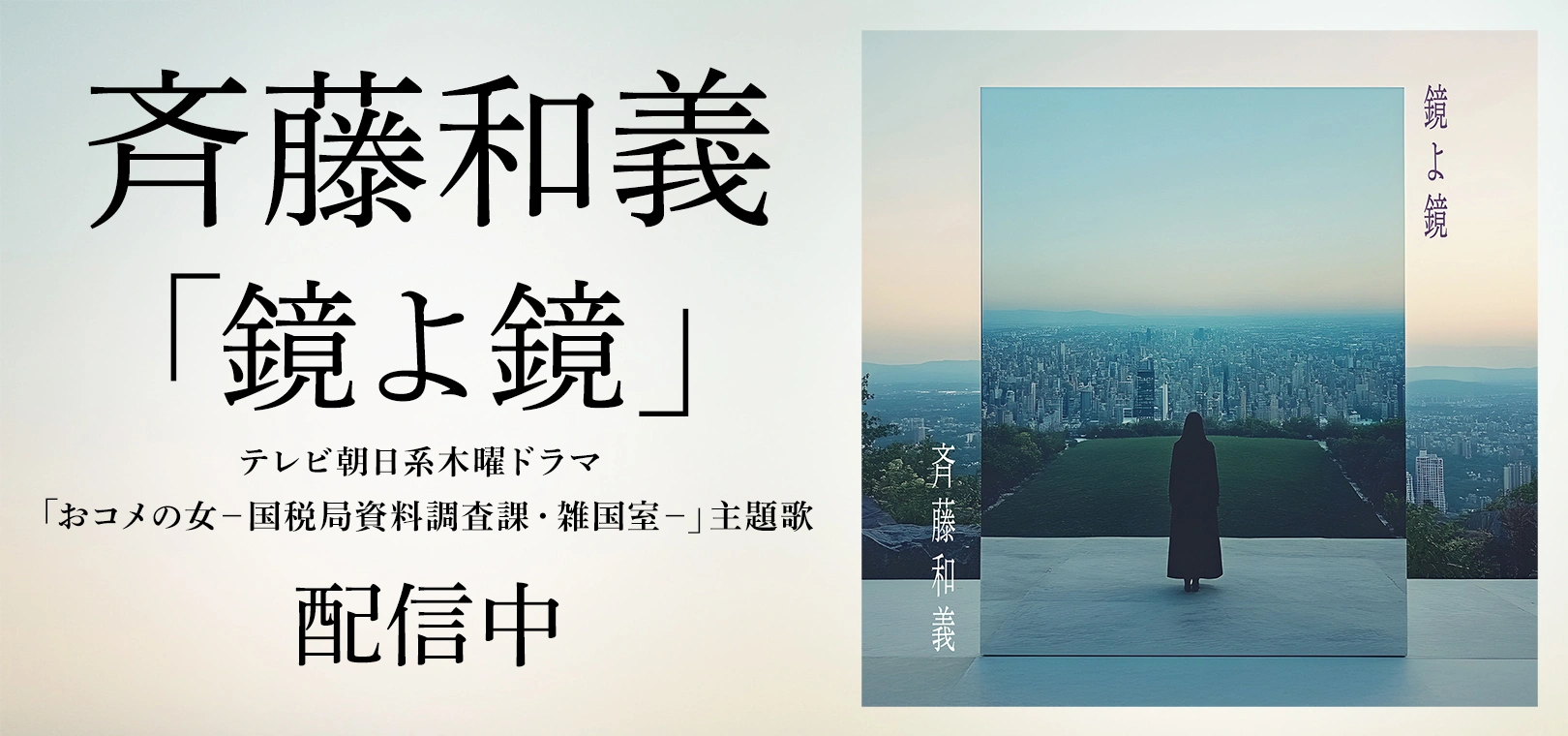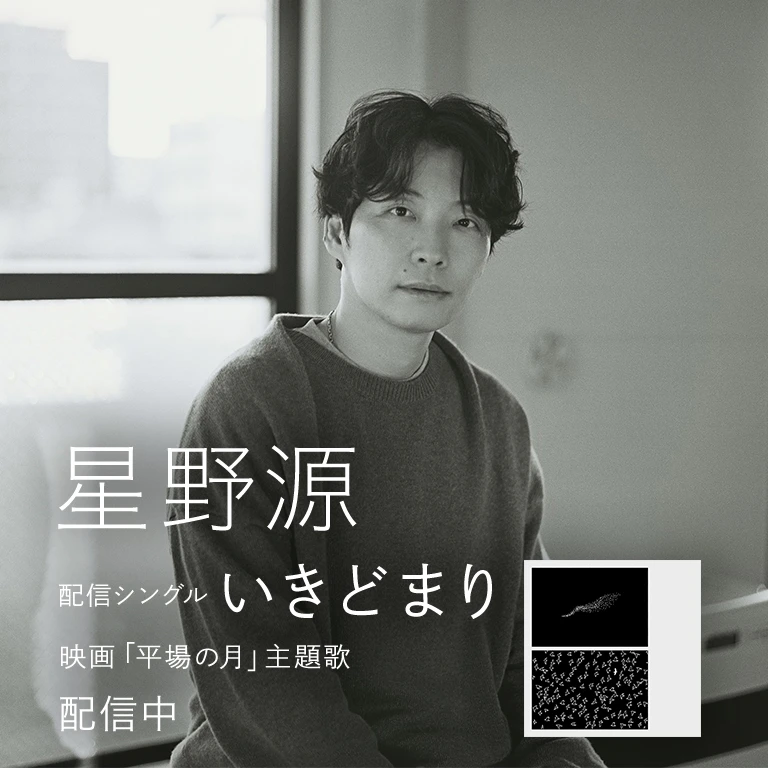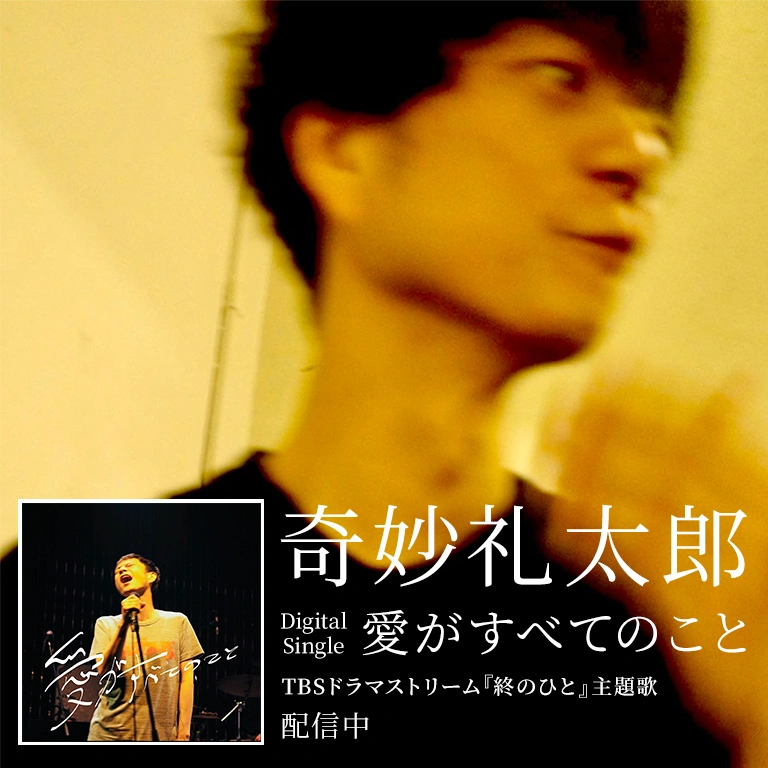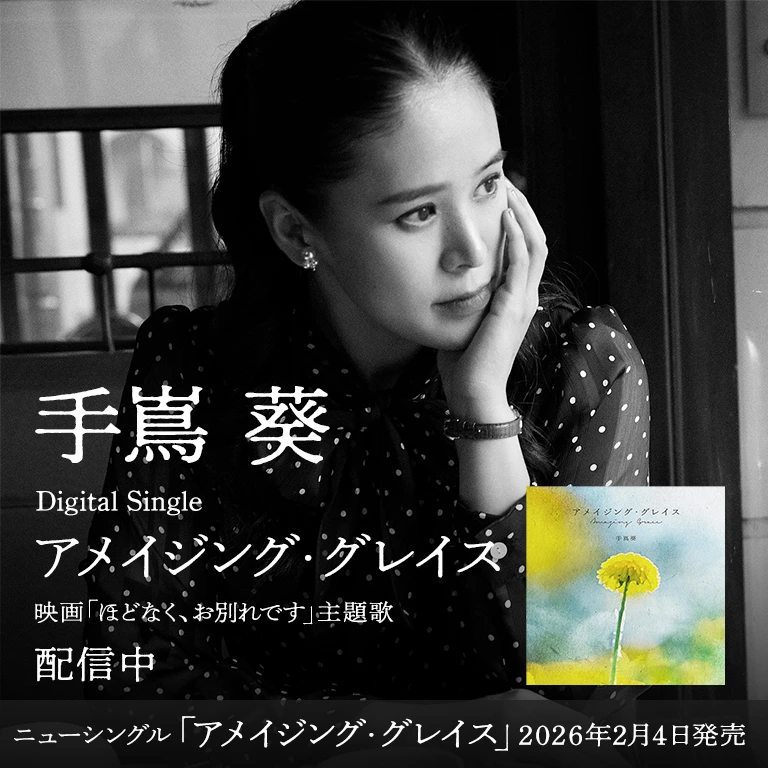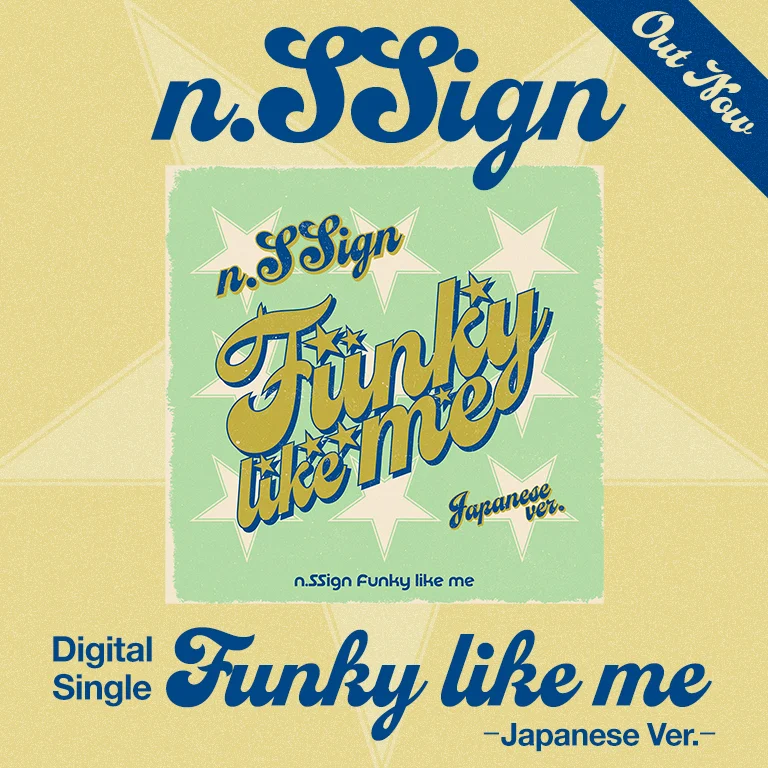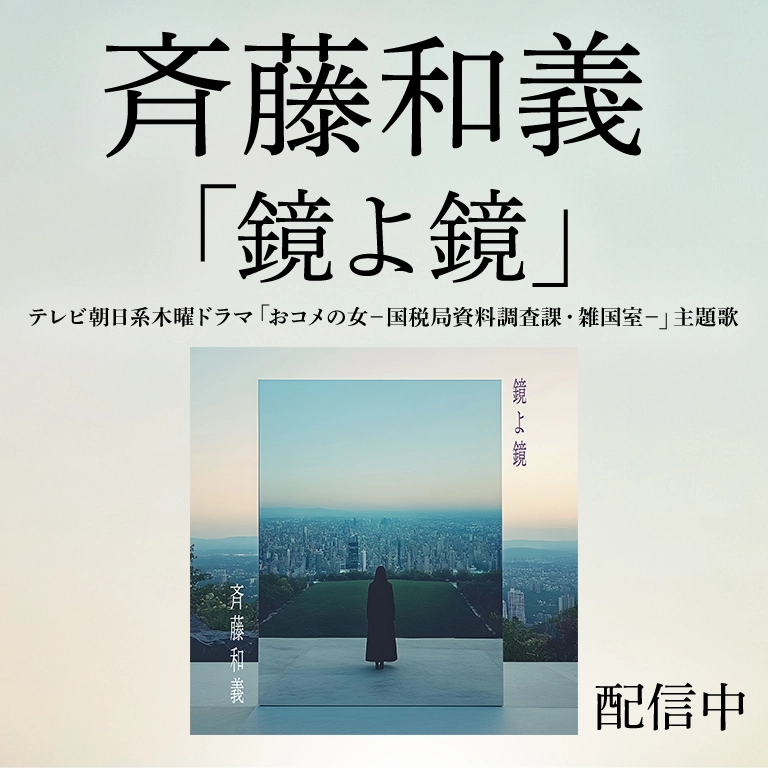アグスティン・ペレイラ・ルセナ/Agustin Pereyra Lucena
CLIMAS~友との語らい
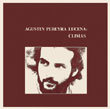
2003.02.05
アルバム / VICP-62187
¥2,640(税込)
Victor
クラブ・シーンからも再評価。典雅なギターの調べによって編み出されるアルゼンチン人のボサノヴァ。自己のスタイルを確立した3rdアルバムを初復刻。
世界初CD化 1973年作品
解説:若杉 実、アグスティン・ペレイラ・ルセナ本人によるライナー付き
-
01
泣いて何になる? Para que chorar
-
02
アンドリーニャ Andorinha
-
03
誰が知っているものか Quem diz que sabe
-
04
テ・キエロ・ディヒステ Te quiero... dijiste
-
05
神のパン Pao de Deus
-
06
私の中の何か Algo de mi
-
07
42年の夏 Verano del 42
-
08
トマーラ Tomara
-
09
偶然の出会い Encuentro casual
-
10
さよならを言うために Pra dizer adeus
-
11
エスポンタネオ(偶発的に) Espontaneo
解説:若杉 実
【ブラジル音楽の長い歴史に溶け込んでいく、典雅なギターの調べによって編み出される、異邦人のボサノヴァ】
どこまでも続くパンパ、万年雪に覆われるアンデス山脈、それでいて洗練された都会の景観をも映し出すアルゼンチンは、一度も訪れたことのないぼくにとっては、あくまでもイメージの中にしか存在しない南米最南の国だ。いつかは訪れてみたいし、ボカ地区のクラブでバンドネオンの律動に合わせて踊りふけることができるなら、いち音楽リスナーとしてこれほどの至福はないに違いない。思うに、これとおなじではないのだろうか、アグスティン・ペレイラ・ルセーナにとってのブラジルとは。
そんな環境下に置かれたアルゼンチン人によるボサノヴァ、それがペレイラという音楽家が描く異国の至宝である。60年代から首都ブエノスアイレスを拠点に、ブラジル音楽に拘泥してきたギタリスト。ブラジル人がタンゴを演奏するなんてそう耳にすることはないけど、彼のようにアルゼンチン人、もしくは当地をベースにする人物がボサノヴァやサンバを好んで演奏していたという例は意外やめずらしくない。すぐ思い当たるのがセバスチャン・タパジョス(生地はブラジルのサンタレン)。彼もおなじくギタリストだ。また、そのタパジョスと親密な関係にあったシンガー、アルナルド・エンリケスは『So Danco Samba』(1976)というソロ・アルバムにてボサノヴァと対峙。歌姫マリア・ナザレーもタパジョス、エンリケスとともにアルバム『Sebastiao Tapajos-Maria Nazareth-Arnaldo Henriques』(1973)を発表しているが、この中でサンバとバロックを融和させたような「Sambachiana」なんてユニークな曲も披露してるし、自身のソロ『Sem Voce』(1976)ではエドゥ・ロボらに影響されたとおぼしきオリジナルを含む、全面的にブラジル音楽に取り組んでいて興味深い。ちょっと重箱の角をつつけば、カイトというギタリストが率いるアルゴ・マスや、ボサノヴァの定番ばかり扱うオス・ボンス・デ・ボサなるグループも70年前後に活動していたことが分かる。このCDにギターとストリングス・アレンジで参加するパウリーニョ・ド・ピーニョも、本オリジナル・レーベルTonodiscにリーダー・アルバムを残していた。それらが、どのような連帯性をもってシーンを形成していたか計りかねるものの、断片的なインフォメーションからかの地のブラジリアン・シーンを読み取ることにもなんら不自由はないだろう。
そんなボサノヴァを志向するアルゼンチン人に、直接的にも間接的にも影響を与えたとされるブラジル人が、ヴィニシウス・ヂ・モライスにトッキーニョ、それにマリア・クレウザだ。外交官にしてシンガーソングライターであるヴィニシウスと、MPB 界のプリンス、トッキーニョはブエノスアイレスやマル・デル・プラタにあるクラブなどでロングラン・ショーをおこなっていた。そのときのドキュメントは、『Vinicius de Moraes en "La Fusa"』(1970)、『Vinicius+Bethania+Toquinho』(1971)といったライヴ盤に記録されている。クレウザのほうは単身で、『Yo... Maria Creuza』(1971)、『Voce Abusou』(1972)、『En Vivo-Grabado en "Edipo Cafe Concert"』(1974)と、計3枚の置き土産を残しているほどだ。
ところで、このペレイラはどうやってブラジル音楽からの薫染を受けたのだろうか。彼の記念すべきデビュー盤『Agustin Pereyra Lucena』(1970)のジャケット裏には、そのヴィニシウス直筆による推薦文が寄せられている。ただし、ペレイラにとってブラジル音楽との邂逅は、ジョアン・ジルベルトバーデン・パウエルのアルバムによってだそうだ。'02年12月号のラティーナ誌に掲載された西村秀人氏による本人へのインタヴューを参照すると、ペレイラの兄がブラジルへ旅行した際にお土産として持ち帰ったのが、そんなふたりのアルバムだったという。ジョアンの卓越したバランソと、えも言われぬ閑吟には感嘆の息を漏らしたものの、本人いわく“歌はあまり得意ではない”ペレイラにとって、むしろ魅力的だったのはギター1本から幻想的な小宇宙を作り上げるバーデンのほう。ペレイラにプロの音楽家の道を選択させるほど、彼との出会いは衝撃的なものだった。近年になって(つまり逝去する直前)バーデン本人に逢うというかねてからの夢が実現したというが、そのとき投げかけた質問には、“アフロ・サンバはどこから来たのか?”というのがあったそうだ!これに対しバーデンは、“私はバイーアに住んだことはなかったが、近所の仲だったピシンギーニャの元夫人が私にアフリカの話をたくさんしてくれたんだ”と答えたという。思うに、ペレイラにとってのブラジル音楽もこれといっしょなのではないだろうか。きっとジョアンやバーデンのアルバムは、彼に多くのことを語りかけていたに違いない。