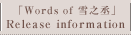






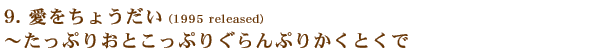

僕が音楽を始めた70年代にはよく「日本語はROCKにのらない」と言われた。確かに、日本にROCKが傾(なだ)れ込んでくる前の歌謡ポップスの歌詞は七・五調を基準にした古めかしいリズムで、こりゃどうやっても英語的なグルーヴは無理だよな、という感じだった。
だが時の流れがその間違いを正した。「日本語はROCKにノラない」のではなくて「日本語をROCKにノセる方法がない」だけだったのである。
例えば、今はもう主流となったが“メロ先”と呼ばれる作詞法。
デタラメ英語で歌ったメロディーが先にあって、それになんとか日本語をはめ込むと“詩先”よりぐっとビートが強調される。メロディーに合わせようとすることで、アーティシペーション(バンド用語で「リズムを食う」と言うが、タイで繋いだ前の小節のお尻の音符からすでに次の音が始まっていること)が大きな意味を持つのだ。そこが言葉の頭になっていると歌のスピード感がグッと増すからである。
もっとリズムを強調するために“韻”を踏んでみたり、英語に似ている単語(しょう=Show、強引=Goingなど)を探してみたり、英語に近い促音(っ)や撥音(ん)、小さい「ょ、ゃ、ゅ」の入った言葉を意識的に使ったりと、桑田佳祐や井上陽水さんや、それこそ多くの作詞家やシンガーソングライター達が、そんな風に様々な試行錯誤を繰り返し、何の不自由もなくRapさえ綴れる時代へと歌詞のスキルを進化させたのである。
ユニコーンの頃から大好きなドラマーだった川西幸一が組む新しいバンドVANILLAに詞を頼みたいと言われた時、ワクワクした事を覚えている。「ROCKにノラない」という呪縛から解かれ、日本語のヤンチャ者になっていた僕は、1行目の「ばったり・へたばったり・くたばったり」の韻を踏んだ言葉遊びをはめ込んだ時、この歌詞に独特のパワーが宿ると確信したのだった。
だから今回、175RのSHOGOとROBOTSのTAKUYAが、この曲を選んで自由に遊びまくってくれたのは何より嬉しいことだ。何かの取材の折、「TAKUYAのギター、JUDY&MARYの頃のより正統派のハード・ロックに戻ってるよね」と言ったら、ライターの方に「いや、きっと雪之丞さんの時代に敬意を表してそうなってるんじゃないですか」と指摘された。
そうだったんだな、TAKUYA、サンキュー!