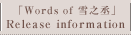








ある程度キャリアを積んだアーティスト同士が出逢う時、お互いの視線の彼方にあるものを確認しあうのには、5分あれば十分だと思う。などと傲慢な言い方をしてしまうのは、すれ違いざまに大黒摩季と交わした言葉の記憶が鮮烈に残っているからに違いない。
2004年の8月、解散後初めてBOOWYのナンバーを歌った東京ドームでの公演を終えた氷室京介が、11月にあえてZEPPで行ったライヴのバックステージで、僕達はすれ違った。マネージャー同士が知り合いだったので紹介され、その時ほんの一言ずつ言葉を交わしたのだった。それは虚飾でも威嚇でもない、氷室京介と互いのリスペクトを確認するための瞬間だった。
氷室京介は、群れない。
“孤高”という美しい言葉で表現することは容易(たやす)いが、それ以上の気高さと厳しさを併せ持った彼を、何と形容すればいいのか?と、いつも戸惑う。
振り返れば、himrock (氷室)とももう10年の付き合いだ。愛しあい、擦れあい、競いあい、高めあい、彼のために生まれた歌詞もすでに30篇。その中でも特に『ダイヤモンド・ダスト』は、僕にとって思い入れの深い作品である。
『氷の世界』というCX系ドラマの主題歌だったせいで、幾つか違うパターンの歌詞を提示する必要があった。だがタイアップのためでなくても、同じメロに別の言葉を作るのは僕にとって珍しいことではない。無いモノねだりをしてしまうのか、しつこい性格なのか...ひとつ書き上げても、もっとイイモノが書けるはずだと、ついAメロの情景設定をイジッてみたり、サビの派手なフレーズを考えたり、思いついては性懲りも無くhimrockにメールを送ってしまう。たぶん『ダイヤモンド・ダスト』の作詞中に綴って捨てたフレーズは、50行近くあったんじゃないだろうか。
そんな風にして完成した『ダイヤモンド・ダスト』だが、himrockはなかなかライヴで歌ってくれなかった。ライヴの選曲にも彼独特の美学があ り、(エルトン・ジョンの数々の名曲を手掛けた)ポール・バックマスターの弦楽器をフィーチャーしたアレンジは、バンドの編成では表現しきれないと諦めていたのかも知れない。
だが、大黒摩季と逢った次の東京公演だったXmasの代々木体育館で、himrockは『ダイヤモンド・ダスト』を歌った。リリースから5年経っても、そのバラッドは凛として潔く、どんなXmas songより輝いていると感じた。そして不思議なことに、その時隣には谷中敦がいて(僕が誘ったのだが)、その夜、このアルバムの話がスタートしたのだった。「絶対『ダイヤモンド・ダスト』は入れましょうよ」と盛りあがって...。
大黒摩季とは今回のヴォーカル・ダビングの際、初めてちゃんと話した。やはり彼女の視線の彼方にあるものは、最初感じたものと間違いではなかった。大黒摩季は、僕の歌詞で氷室京介をカヴァーして欲しかった気持ちを、感動的なほど理解してくれている。このアルバムに隠されている、幾つものバトンのことも。